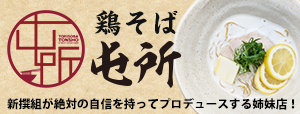編集部
AFTER SUGIHARA SETSUZO KOTSUJI's AID TO JEWISH REFUGEES 命のバトンをつなぐ人々Part2-1
2019-04-27

(左から)リーベ・ゲフト寛容博物館館長、広瀬佳司氏、通訳の内藤あすか氏、山田純大氏による質疑応答セッション=3月27日、寛容博物館、ロサンゼルス
1940年、杉原千畝がリトアニアで発行したビザを持ったポーランド系ユダヤ人たちは、その後、どうなったのか。杉原が発行したビザが“命のビザ”と換わった背景にいたもう一人の人物、小辻節三についての講演会、「After Sugihara Setsuzo Kotsuji's Aid to Jewish Refugees」が、3月27日、ロサンゼルスにあるサイモン・ウィーゼンタール・センターの寛容博物館にて、在ロサンゼルス総領事館、サイモン・ウィーゼンタール・センター、日米文化会館の共催で催された。
ノートルダム清心女子大学教授の広瀬佳司氏は、杉原千畝・小辻節三に関係する歴史的、思想・宗教的な背景を説明し、これまでの解釈では不十分な点を指摘しながら、二人の接点をまとめて講演し、一方、俳優の山田純大氏は、小辻の家族との交流を通し、著書『命のビザを繋いだ男 小辻節三とユダヤ難民』を執筆するまでの経緯や小辻の活動について講演した。
この二人の講演を振り返りながら、小辻節三の功績を紹介するパート2。
前回は、広瀬佳司氏の講演から杉原千畝がビザを発行した時代背景や杉原の歴史について主に紹介した。
杉原が発行した通過ビザを持った2139人のポーランド系ユダヤ人難民たちが、次々と福井県敦賀港に到着し、多くが神戸にあるユダヤ人コミュニティへとやってきた。
通過ビザの期限は10日間。ようやく日本にたどり着いたはいいが、10日間で行き先を決めるのは非常に厳しい状況だった。打開策もないまま、時間だけが過ぎ、ビザの期限切れが目の前に迫っていた。
この時、神戸のユダヤ人協会が助けを求めたのが、ヘブライ語学者の小辻節三だった。小辻は杉原と違い、外交官でも政治家でもない、いわゆる一般人だった。
なぜ、小辻だったのか?どのようなつながりが、小辻とユダヤ人にあったのだろうか? 
(左から)リーベ・ゲフト寛容博物館館長、広瀬佳司氏、通訳の内藤あすか氏、山田純大氏による質疑応答セッション=3月27日、寛容博物館、ロサンゼルス
広瀬氏が注目したのが小辻の生い立ちだった。
小辻は、京都市にある下鴨神社の神官の息子として1899年に生まれ、将来は神官にと期待されていた。しかし、13歳の時に古本屋で買った旧約聖書を読み、深い感銘を受けた小辻の人生は一変した。
1964年に英語で出版された小辻の回顧録「From Tokyo to Jerusalem (東京からエルサレムへ)」から、次の箇所を、広瀬氏は引用した。
「There is also a distinction made between holy and unclean . . . It is not an exaggeration to say that the religion of Leviticus is a kind of Hebrew Shinto.(神聖なものと不浄なものの間でできる特質もある...レビ記の宗教はヘブライ語で書かれた神道の一種だと言っても過言ではない)」
広瀬氏は「小辻が幼少の頃、ユダヤ教は日本ではまだ広く知られていなかったが、おそらく小辻は伝統的な神道の儀式を通してユダヤ教に類似した神秘的な同等な物を経験したのでしょう」と語り、小辻がその後にユダヤ教に惹かれていく自然な流れは、すでに小辻青年の中に芽生えていたようだ。
小辻は17歳になると、神道ではなくアメリカの長老派の大学、明治学院大学に入学し、聖書を学びキリスト教の牧師になった。しかし、キリスト教への疑いを心に抱いていたという。
1923年、24歳で、キリスト教徒のミエコと結婚し、牧師として約10年間を過ごした。その後、旧約聖書を学ぶため、ニューヨークの大学に留学し、バークレーにあるパシフィック宗教大学で「The Origin and Evolution of the Semitic Alphabets」と題した論文で博士号を取得した。
その後は日本へ帰国し、1931年に青山学院大学でヘブライ語の教授となった。しかし腸チフスを患い、1933年に退職。小辻家は収入もなくなり、経済的にも非常に苦しくなった。
1938年、小辻はもう一人の“命のバトン”をつなぐ人物と出会った。当時の南満洲鉄道総裁で、後の外務大臣、松岡洋右だ。松岡は、ユダヤ人の文化などを熟知した小辻を、満州のユダヤ人問題顧問として招聘した。
(つづく)
=Tomomi Kanemaru
この記事の他のパートは以下からご覧ください。
▶︎ 1
▶︎ 2-1
▶︎ 2-2
▶︎ 3-1
▶︎ 3-2
▶︎ 4-1
▶︎ 4-2
▶︎ 4-3
▶︎ 5
▶︎ 6
▶︎ 7
▶︎ 8-1
▶︎ 8-2
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 日刊サン編集部
日刊サン編集部