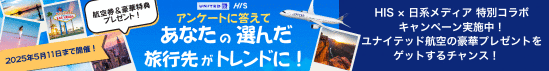スペシャル座談会 在ロサンゼルス総領事ご夫妻 ”世界の動向”と”私生活”を語る
ゲスト・武藤顕氏/三佐子夫人 聞き手・後藤英彦(元時事通信LA特派員)
武藤顕氏。 インド・ニューデリー生まれ。1985年東大経済学部卒、外務省入省。在米日本大使館、在ロシア日本大使館勤務。2012年ボストン総領事、15年内閣官房内閣審議官、19年在ロサンゼルス総領事(現職)。
前半は在ロサンゼルス総領事の武藤顕氏と、後半は三佐子夫人を交えての座談会。武藤氏には日米関係や日本を取り巻く諸事情について、三佐子夫人には私生活を中心にアクテイブに語ってもらった。
後藤 武藤在ロサンゼルス総領事をお迎えしています。後半で三佐子夫人にも参加していただきます。初歩的な話から始めますが、外交上の取り決め、条約と協定の違いは何ですか。
武藤 呼び方の問題だけで、国際約束という意味では同じです。
後藤 条約のほうが強いと思っていました。
武藤 そうですね。条約のほうは国会の承認を要することが多いです。国際約束はそれぞれの国でしかるべき法的手続きをすました後で発効することになっていますが、国会の承認を要する比較的比重の重いものを条約と称することが多い。国会承認条約と国会承認を伴わない行政取り決めとがあって後者のほうを協定と称することが多いです。
後藤 では日米関係で一番重要な取り決め、日米安保条約とは何ですか。
武藤 二つあります。一つは日米安保条約第五条。これは日本が武力攻撃を受けた時にアメリカが日本を守るために措置をとるというコミットメント(公約)。もう一つは第六条。日本の安全と極東の安全と維持向上のため、アメリカが日本の領土内に米軍基地を設けることができる。前者は他国の武力攻撃に対して日本を守る。後者は日本のみならず極東の安全維持向上のために米軍施設を使う。この二つがこの条約の柱です。
後藤 この条約は日本にとってどんなメリットがありますか。
武藤 日本の防衛の大宗をアメリカに委ねることが出来る。敵が攻撃してきた時に敵を跳ね返す役割をアメリカが担ってくれる。核兵器を持っている敵に対しても日本が核武装をする必要がなくアメリカに頼りつつ安全保障を考えればいい。戦後のいわゆる吉田ドクトリンと言われるもので、日本は重武装をせずに経済発展に集中できたわけです。
後藤 あれはニクソンと佐藤総理との取り決めでしたか。
武藤 いいえ。サンフランシスコ講和条約(一九五二年)を踏まえた吉田ドクトリンは佐藤ニクソンの沖縄返還協定よりはるか前のことです。
後藤 ああ勘違いしてました。吉田総理(在任一九四八年十月~五四年十二月)の吉田ドクトリンと佐藤ニクソンの沖縄返還協定調印(一九七一年)をごっちゃにしてました。そして在日米軍駐留経費負担特別協定というのがありますね。この協定における日本とアメリカの駐留負担比率は何対何ですか。
武藤 そこには書いてないと思います。
後藤 では経費の負担について定義付けがしてありますか。
武藤 いいえ。その時々に交渉して決めるんです。
後藤 ではトランプなんかにかかると日本はいつも力負け。アメリカに押されちゃいますね。
武藤 そこは私が冒頭で二つと言いましたように、前者(日米安保条約第五条)はアメリカの日本防衛の義務なのですが、後者(同第六条)では、日本の安全のみならず極東の平和と安全のためにアメリカが日本で基地を使用できる。これは日本の利益でもあるが、アメリカにとっての利益も大きいんです。
後藤 わたしはアメリカの利益のほうが大きいと思いますけど・・。
武藤 なので日米安保条約は決して片務的条約じゃない。総合するとアメリカにとって物凄くメリットのある条約なんですね。アメリカがアジア太平洋国家として居続けるために不可欠な条約です。
ですから駐留経費問題でも時の総理の力関係と言う以上に、構造的に日米安保条約というのがアメリカをしてアジア太平洋国家たらしめる、ある意味大きな力を与える条約なんです。だから、日本を防衛する事だけがアメリカの負担という立場に立たずにアメリカの安全保障のためでもあると説明しているのですが、そこはなかなか・・
後藤 理解が得られないと・・。トランプは強引で思い込みが激しいから。次に日米地位協定ですけど、米兵が犯罪を犯すたびに問題になりますね。犯人をこちらに渡せと言っても容易に応じない。日本側が弱腰なのか、米側が日本の意向をまともに受けないのか。報道等で見聞きする限り、日本側のパンチが弱い気がします・・。
武藤 それは我々の説明の弱い所があるんだと思います。ただ実際のところは起訴のタイミングも含めて、当初より日本の都合が良いように運用が変わってきています。地位協定を通じ合同委員会の協議を通じて日本側がモノを言えるようになってきています。
後藤 日本の主張が早く通るようにしてほしいです。不平等に感じることと言えば、国連の敵国条項。同じ三国同盟(一九四〇年成立)のドイツとイタリアは敵国条項から外れているのに、日本は依然、敵国の扱いになっている。なぜ敵国条項を外すことができないのですか。
武藤 敵国条項が残っているのは事実ですが、歴史的使命はもはや終わっています。
後藤 そうですね。日本人として面白くない。何がネックになっていますか。
武藤 日本人の感情としては嫌なことです。ネックは安保理(国連安全保障理事会、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国の五カ国で構成)です。
後藤 安保理の中国がネックになっているという意味ですか。
武藤 中国、場合によってはロシアが(日本を除外することに)抵抗する可能性がある。こういうことを根こそぎなくすには、安保理を改革をしなくては・・。国連改革の中で安保理の扱いを議論しなくてはいけません。
台湾有事
後藤 そうですね。安保理は大問題ですね・・。それから、日本人は平和ボケってよく言いますね。日本人の平和ボケを百とすると、アメリカはゼロ、中国もゼロ、韓国は五〇などと数値化すると分かりやすい。外交官がそれをどう感じておられるか知りたいのですが・・。
武藤 身近なところで言うと、台湾有事(中国が台湾に侵攻、戦争になること)はアメリカの専門家の中でも現実の議論になりつつある。日本で現実の世論になっているかというとかなり開きがある。アメリカでは台湾関係法(TRA)、これはアメリカが中国との国交を回復した一九七八年以来、戦略的曖昧さ(strategic ambiguity)といって、敢えてそこに防衛コミットメントを与えていない。
安保条約第五条と違って台湾に対しては、中国が台湾との問題を平和手段以外の形、つまり武力侵攻で解決しようとすることはアメリカにとって重要な懸念を引き起こす、と言っているだけなのです。
日米安保条約第五条のような防衛コミットメントを与えていないのですが、これが米中関係において、もはや時代にそぐわないんじゃないかと・・即ち中国が攻めてくる可能性があるから、それに対する抑止力を明確にするため、伝統的な戦略的曖昧さから戦略的明確性(strategic clarity)を導入すべきだと・・。
つまり日米安保条約に相当する防衛コミットメントを台湾に与えるべきとの議論が行われているが、その点は日本の世論レベルでは共有されていないと思います。
後藤 外交官の思いと一般庶民の思いには大きな開きがありますね。そこで思うのですが、日本人にはリアリズムがありませんね。
武藤 ないですよ。折角の機会なので申しますと、日米安保条約の第六条における極東の範囲について日本政府は一九六〇年二月の「極東条項の範囲とは」で、「大体においてフィリピン以北、日本周辺、韓国及び台湾を含む」としていて、台湾で有事が起こると、日本の米軍基地を使用することはある意味で容認している。だから台湾の有事は日本も自分の問題として考えないといけない。沖縄の米軍基地が敵の攻撃対象になるということ。日本においてこういう意識が希薄なのを憂慮します。
後藤 韓国の平和ボケ度はどうでしょう。
武藤 韓国は北朝鮮があるので日本ほどではないけれど、中国を意識しているかというと日本とどっこいじゃないですか。
後藤 中国には頭を下げっぱなし。歴史的にもずうっと頭を押さえつけられてきたから、それが彼らの民度にも及んでいると思うのですが・・。序でにお聞きしますが、当地の韓国総領事、中国総領事との交流はありますか。
武藤 ありますよ。あえて積極的にやっています。
後藤 それはいい。ゴルフでもやっていると違いますよね。先ほど北朝鮮の話が出ましたが、北朝鮮のミサイルがアメリカに届くとか届かないとか・・。この場合アメリカと言えば西海岸。大都会のロス、米軍事基地のサンデイエゴ、サンフランシスコあたりがターゲット。
武藤 グアムまでは届くわけです。その次は本土、西海岸になりますね。
後藤 北朝鮮は何を考えているのでしょう。小さな国が大国に挑むなんてあり得ないのでは。
武藤 あり得ないと言っても我々にも苦い歴史がありますから。アメリカと喧嘩をしたのは我々日本で、人のことは言えません(笑い)。
後藤 ご専門のロシアについてですが、ロシア人気質ってひと言で言うと・・。
武藤 ひと言で言うと、自分たちのアイデンテイテイを見つけられなくて永遠にさ迷っている。西洋人には拒絶され、アジア人と言ってももともとスラブ人は北欧出身なんですね。
後藤 「モンゴルのくびき」(一二四〇~一四八〇年の二百四十年間、ロシアがモンゴルに支配されていた時代のこと)じゃないけど、東洋の血がかなり入っている。
武藤 「モンゴルのくびき」でモンゴルの血が入ったんだけど、彼らが望んだ血ではないので、彼らの誇りにならない、心の傷なんですね。で、ヨーロッパ人にもアジア人にもなれなくてどういうふうに生きたらいいか常に悩んでいる。
後藤 さ迷える羊(stray sheep)ですね。ロシア文学が好きで、何を読んでも東洋の匂いがする。ドンコサック(封建権力を逃れてドン川下流域に住んだ人々による軍事組織)とか農奴の風土・・プーシキンの「大尉の娘」、ドストエフスキーの「貧しき人々」、チェホフの「桜の園」、ゴーゴリの「検察官」なんかみんな東洋の匂い。
武藤 通じるところがありますよ。
後藤 フランスもの、イギリスものはアチラ様、ロシアはこちらって感じ・・。
武藤 ただしわかるということと友達になることは違います。
後藤 友達になれないんですか。
武藤 (友達は)いますよ、だけど簡単じゃない。二十回会ったからと言って信頼関係を築ける訳じゃない。
後藤 友達になるのも容易じゃないと・・。じゃあプーチンの本音(対日本)は何ですか。
武藤 プーチンの本音は安全保障の確保。日米の離間(相互の仲をさくこと)ですね。
後藤 北方領土の位置づけは?
武藤 日米を離間(互いの仲を裂くこと)させる道具というか踏み絵です。
後藤 日米関係を踏み絵にして日本がロシア側に寄ってきたら、もっと良い条件を出すという意味ですか。
武藤 いや、日本に領土を還すのであればロシアの安全が日米同盟により損なわれないことを日本は示す必要がある。
後藤 誰でしたか、二島返還した場合でもアメリカの基地の敷設を認めたりすればただちにご破算だと。
武藤 ええ、それに近いことを言っていますね。アメリカがミサイル防衛基地を作るのは北朝鮮のせいだと言ってもロシアはハナから信じていない。ロシアに近づくのを嫌がる。旧ワルシャワ条約諸国(旧ソ連側)がNATO(西側、北大西洋条約機構)に加盟するとき例えばポーランド、ハンガリー、チェコ、ルーマニアに対して、イエルチン大統領はNATOに加盟するのであれば旧ソ連圏にNATOのアセット(軍事施設)を持ち込まないことを確約してくれとクリントンに迫った。
クリントンは紙では認めなかったが、ロシア側の言い分は“口頭了解”をもらったとしており、そこが食い違っています。
後藤 日本人はそういう肌合いに頓着がありませんね。
武藤 アメリカ側はそんな了解はない、ロシアが騙されたというのは根拠のない話だと。実際は藪の中だけど、ロシア側は”口頭了解“を貰ったのに反古にされたと。特にルーマニアにイージス・アショア(米軍地上配備型のミサイル防衛システム)を持ってきたり、ミサイル・デイフェンス・システムをチェコとかポーランドに配備したので、約束違反だと言っています。
後藤 では中国、習近平の本音(対日)は何でしょう。
武藤 米日離間(互いの仲を裂くこと)じゃないでしょうか。
後藤 米中でハワイを起点に地球を中国圏とアメリカ圏の二つに分けようという習近平の発言がありましたね。日本は中国に組み込まれるのでは・・。
武藤 沖縄は向う側。でも日本を取るとはさすがに言わないでしょう。
後藤 あれ、本気で言っていますよね。
武藤 本気ですよ。
後藤 習近平は岩礁を島にするなど領土拡大に躍起。黙っていると地球の地図がどんどん書き換えられていく。
武藤 ですから日米関係をこれまで以上に揺るぎないものにしないと・・。
後藤 トランプにそれが通じますか。「俺の国の若者は血を流して戦っているのに、お前たちは何だ。血を流す代わりにただカネで対応している。血を流すのが嫌ならせめて軍艦を買え、戦闘機を買え」という理屈。

米任せの安保
武藤 何と言ってもトランプさんはアメリカの大統領。大統領にアジア太平洋の平和に日本がどれだけ貢献しているか、今後どれだけ貢献していくか、よく承知してもらう。そのためには安全保障面での貢献ですね、既に海上自衛隊は世界中に船を派遣、演習をしたり、米軍と一体であることを示すため、南シナ海に行って合同演習をしたり、潜水艦がオペレーションを拡大したりと皆さん、大変体を張っておられる。
後藤 いつでしたか、たくさんお金を出して貢献したのに、お金の貢献は軍事貢献として見てもらえなかった・・。
武藤 イラク戦争。クウエート侵攻の時です。
後藤 湾岸戦争の時でしたか。血を流す貢献でなくては駄目。お金の貢献は印象としてとっても希薄。でも応分の血を流せなんて日本人に言おうものなら大変で、アレルギーを起こす。徴兵と言えば必ず戦争と結びつける。リアリズムを欠くと言えばそれまでだけど、スイスなんか十年の徴兵制を敷いている。軍務期間を何回かに分けて兵役を終えることもできる。軍隊ではタダでたくさんのことを学べると、徴兵義務はむしろ歓迎される向きさえある。
日本の旧軍隊は連帯責任などと言って鬼軍曹が毎日のように全員に鉄拳制裁を加える。あれが日本人の軍隊イメージになっていると通産大臣当時の中曽根さんがおっしゃっていた。旧軍隊のイメージが強くて、スイスのような平和軍隊に結びつかない。
武藤 そういう面もあるが、後藤さんのおっしゃるリアリズムを日本人は欠いている。冒頭に戻って吉田ドクトリンというのは中共もソ連も参加しない中での条約(サンフランシスコ講和条約)締結で、中共、ソ連とは別個の交渉という中での戦後復帰だった・・。
アメリカ依存を選んで経済的には繁栄したが、その代償は安全保障政策がアメリカ任せになったこと。イラク戦争の連合軍クウエート侵攻の際、莫大なお金を払ったのに、クウエートの戦勝感謝広告の中に日本の名前を入れてもらえなかった。戦後外務省組としては非常に屈辱的な経験でした。
後藤 リアリズムがないというのは日本人みんなのもので、たくさんの金を出したから(連合軍に)貢献したと思い込んでいたが、日本人の期待する評価は得られなかった.唖然としました、あの時は・・。
武藤 安全保障に貢献していなかったからです。そもそも安全保障政策って(日本に)なかったんですよ。いかにリアリズムに欠けていたということです。どこの国も外交政策と裏腹の安全保障政策を持っている。日本にはそれがなかった、安全保障政策はアメリカが作るから余計だった。日本が作ると相いれないものになるから、そこは封印してきた。
後藤 ある意味、アメリカへの忖度。
武藤 国際情勢が刻々変わっていく中でこれでいいのか、(前総理の)安部さんはそういう意識をもっておられた。安倍さんの言っておられた積極安全保障政策はリアリズムに基づくものに作り変えるというので、安全保障政策が作られるようになったんです。
後藤 文字としての政策表現が抽象的すぎる。新聞が回覧板のようにそれを丸写しするから、国民には理解できない。易しく説かないから漫画に逃げる。先日、大隈重信の演説集を読んでいたら、選挙の投票率が低いのは政府が悪い。民意を聞く気があるなら、国民に選挙の重要性を教える努力をしろと。抽象論は駄目と声を大にして言っているんです。
武藤 (うなずく)
後藤 えー、あの日本語をしゃべる「アメリカ人の日本語話者の会」、(総領事館の何らかの支援を得て)続けたら面白いんじゃないですか。英語が不得意で消極的な日本人に頼るより、積極的なアメリカ人の日本語話者を活用するほうが日本理解の早道では・・。他の州にも活動の輪を広げていけば日本理解のウエーブになるのでは・・。
武藤 コロナ禍でやれなかったけれど、業種ごとに呼んで話を始めます。最初は大学の先生を予定しています。
後藤 それから日系人の勲章の対象が陽の当たる人ばかりになっている。総領事も首席領事も二年余で帰国されるから、情報が不足している。老人ホームでの例で尾籠な話ですが、うんちが出なくて苦しんでいる老女の肛門に指を突っ込んで出してやるような人がいるそうです。ボランテイアの女性だそうだけど、こういう人にこそ勲章をあげる。そういう勲章であってほしいと思います。
武藤 おっしゃる通り。そういう方がいらっしゃったら、是非、おっしゃってください。
後藤 はい。ではここから話題をガラっと変えて、総領事の奥様、三佐子夫人をお迎えしてお話を伺います。えー、結婚されてロサンゼルスは何カ国目ですか。
夫人 国(大使館勤務)としてはソ連時代のモスクワ、アメリカ・ワシントンDCの二カ国、海外勤務はオックスフォード、モスクワ、ワシントンDC,ボストン、スタンフォード、ロサンゼルスの六か所です。
後藤 よそと比べてロスはいかがですか。
夫人 それはもう天国のようなものです。
後藤 ロス・アンゼルス(英語のエンゼルの意)と言いますからね。
武藤 天国と言う意味は温かいということ。これまでは凍てつくような所ばかりでしたから。
後藤 お忙しいでしょうが、お二人で外出なさることは?
夫人 グリフィスパークにトレッキングに行きます。
後藤 あそこにジェームス・デイーンの胸像が立っています。
夫人 それは知りませんでした。
後藤 グリフィス天文台の正面右側の外にあります。ほかにお気に入りの場所は?
夫人 おととしから去年まで十ヵ月いたスタンフォード大学で主人がビジテイング・スカラー(客員研究者)をしていて、大使館とか総領事館と全く関係なく、汚いアパートに住んでいましたが、結構いろんな人に出会えて楽しかったですね。そこで出会った人と週三回ぐらいいろんなセッションを持ち、インタナショナル・ポエトリー・セッション(国際詩歌セッション)だのレイシャル・デスククリミネーション(人種差別)についてのデイスカッションだの。週三回ぐらいオンラインで呼ばれてもう大変・・。
後藤 アパートと言うのは大学の寮?
夫人 いいえ、普通のアパートです。そこでオンラインで知り合ったスタンフォード大学の方々とコロナ後、発信しまして、ポエトリー(詩歌)では美智子上皇后の「ねむの木の子守唄」、あれを紹介させていただいて、その英訳はTakako Lentoさんと言って日本の俳句とか谷川俊太郎さんとか永瀬清子さんの本や詩を翻訳していらっしゃる方なんですが、その方に英訳をお頼みしたものを紹介したり・・。
その中の永瀬清子さんの「大いなる樹木」、この本は英語と日本語で書いてあり、その詩を読ませてもらったりとか。この方はハンセン病の隔離施設を四十年間通い続けて詩を集め作られてもいる。
後藤 日本文化のほうはいかがですか。着物は一人で着れますか。
夫人 当地は日本文化が盛んですね。私は一応草月流、師範まではとりましたが、まだ下のほうで北島(蓉幸)先生のレッスンを受けさせて頂いています。着物は自分で着れます。
後藤 ほかに趣味は?
夫人 こちらに来て納豆を作っています。日本から納豆菌を取り寄せています。(納豆を作る白い容器を手に持って)これがヨーグルトメーカーなんですが、四五度、二十四時間でできるのです。大豆を圧力鍋で柔らかく煮る。耳かき大のスプーンの五分の一ほどの粉末納豆菌を溶かしたものを入れるだけで二十四時間でできるんです。
納豆って血栓を溶かす、心筋梗塞や脳梗塞の予防になる。美容効果もある。がん予防、骨粗そう症の予防にもなる。よいことばかり。わたくし、花粉症なんですね。納豆は花粉症にも効くというので、お医者様に納豆キナーゼの溶剤を戴いて。それも日本から持ってきています。納豆は毎日食べます。
後藤 総領事も食されますか。
武藤 食べさせられています(笑い)。
後藤 では次、愛読書を挙げてください。
武藤 やっぱり司馬遼太郎、坂の上の雲。
後藤 わあ(笑い)、これは握手(二人立ち上がって握手を交わす)。わたしも七、八回読んだら所々で描写がダブっているんです(四年余の長期にわたり連載したのでいくつか重複がみられる)。奥様はどうですか。
夫人 司馬遼太郎も好きですが、Southlandと言って日系のNina Revoyrという方が書いたものですが、一九六五年のワッツ暴動を背景に詳しく書いてあって勉強になりました。日系社会と黒人社会のことなど、サスペンスなんですが、その時代のことが良く書けていました。
後藤 お二人のなり染めは?
夫人 わたくしの母と主人の母、知人の友人が紹介してくれました。
後藤 お見合いですね。どこが気に入りましたか。
武藤 飾らないところ。
夫人 主人はすごく優しく知的でした。大学時代の卒業旅行に東南アジアとかに行った時、マレーシアとかフィリピンとか反日のところで、自分の親は戦争で殺されたとか聞かされ複雑な気持ちでいて、日本人としてどうしたらいいかって悩んでいた・・。
何回か会った時にそんなわたしを包み込んでくれたんです。それに惹かれたところが大きいです。彼と結婚して歴史などいろいろ教えてもらって解釈の仕方とか日本人としての生き方とか結構正しいことを言うなと。たまにはちょっと偏っているんじゃない?と思うこともあるけど、尊敬しています。

喧嘩はする
後藤 喧嘩はします?
夫人 します。
武藤 しょっちゅうです(笑い)。
後藤 原因は?
夫人 些細なことです。
武藤 そう言いながら強いんです。歴史観も違うし・・。
後藤 総領事を観ていると、硬派ですよね。
夫人 硬派です。
後藤 高下駄に袴を着たら似合うだろうなって・・(笑い)。
武藤 僕は半分インド人(インド・ニューデリー生まれ)、いや半分とは言わない、三分の一はインド人。生粋の日本人ではないな、日本を外から観ている感じなんです。比べられるんです、いい加減な外国人が多い中でいかに日本人が真っ当かって。それを外に向かって言うのが自分の任務、ミッションだと思っているんです。
後藤 この言葉は言わぬほうがいいな、彼女が怒るからっていう禁句がありますか。
武藤 それはもう殆どですよ。すぐ怒られます(夫人、爆笑)
後藤 ドラッガーでしたか、命令形はよしなさい、いつも依頼形にしなさいと。「これしろ」は駄目。「これにしてくれる」と言えば人間関係も膨らむと。
武藤 後藤さんね、「これしろ」なんて言ったらもう終わっちゃいますよ(夫人、爆笑)
夫人 済みません、かかあ天下で(爆笑)
後藤 かかあ天下は夫婦円満の秘訣と言いますね。でも出来の悪い奥さんだったら例えば「外交官のくせに」なんて禁句をすぐ吐いちゃう。
夫人 わたくし、そんなこと思ったことありません。
後藤 二人の関係がよくわかりました(笑い)
夫人 主人が上に居てくれたほうがよかったのかしら・・(笑い)
後藤 お子様は?
夫人 二人おります。娘でございます。明日結婚、入籍します。
後藤 (あちらに)行かないんですか。
夫人 ええ、上の娘が今年の六月だかに「マム、エンゲージ(婚約)した」って言うので、のけぞっちゃったんですけど、娘はみずほ銀行にいたんですけど今年一月、イギリスのコンサルタント会社プライスウオーター・クーパーに転職し、そこで日本人エンジニアの方と一月に知り合ったそうです。それで慌てて主人と会いに行き、すごくいい方だったので安心しました。
後藤 お目出度いお話を伺いました。今日は貴重な時間を有難うございました。

(写真提供: 在ロサンゼルス総領事館、水野穣氏)