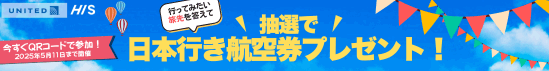第11回広島大学からの医師団がLAで検診を開催
2015-08-21
広島大学病院の医師団が8月6日から22日までロサンゼルスに滞在し、ロサンゼルス在住の日本人や日系人の健康診断を行っている。会場の南加広島県人会館には、連日40人以上の人々が訪れ、日本語で日本からの医師に質問ができるので好評だ。
この検診は、広島大学病院の第二内科の医師らが、「日本人の遺伝子を持ちながらアメリカで生活する日本人または日系人は、食生活も運動習慣も日本と異なるので、生活習慣病といわれる肥満症、糖尿病、脂質異常症などに違いが出るのではないか」という点に着目し、1970年代から始まった。それ以来、広島、ハワイ、ロサンゼルスの3カ所で行われ、海外では4、5年毎に行われているという。
検診では心電図、頸動脈のエコー、眼底検査、血液検査、栄養や運動量の聞き取り調査などが行われ、採血された血液は広島大学に持ち帰られラボで検査される。全ての検査値が出ると、医師が検査値を読み、それぞれの受信者へコメントを付けて、二ヶ月後に検査結果をアメリカへ送る。
検診日程の後半、医師団のリーダーとなった大野晴也医学博士は、「生活習慣病は半分が遺伝子、もう半分は環境が影響すると言われています。同じ遺伝子で、生活が異なるとどういう違いがでるのかを見る研究が少ないです。この検診によって、予防や治すためのアプローチは何がいいのか、どんな薬がいいのかが明確になるので、大変役に立ちます。また研究が長ければ長いほど、研究の価値が高くなりますし、これほどに経過を追わせていただいている研究はなかなかないので、これからも大事にさせていただければと考えています。
またハワイやロサンゼルスには日系人が多く、県人会もしっかりある地域なので協力的な方々が多く、リサーチがとてもやりやすいのはありがたいです」と述べた。
第1回目から検診に協力している南加広島県人会(盛岡会長)の芥川さんは、「日本語でドクターに気軽に質問ができるので、受けられた方たちには喜んでいただいています」と、検診受信者リストを夜遅くまで作成する日々が続いたにもかかわらず、笑顔で話した。検診前後も入れて約3週間のボランティアをする広島県人会の皆さんにも検診は支えられ、今回は約700人が検診を受ける。 
第11回目を迎えた広島大学の医師団による検診は医師団と南加広島県人会のみなさんによって成り立っている
= Tomomi Kanemaru