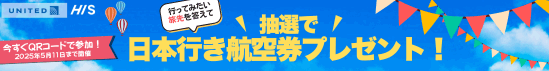米国書道研究会創立50周年記念 特別インタビュー②
2015-10-09
書家 生田 博子
夫と師の死後、独りになり、これからが勝負
(左から)堀之内秀久在ロサンゼルス日本国総領事、生田博子氏、堀之内サビーン総領事夫人
半世紀もの間、アメリカで日本の書道普及に貢献してきた米国書道研究会は、10月4日から18日までの2週間、リトル東京の日米文化会館(JACCC)1階のドイザキ・ギャラリーで「創立五十周年記念日米合同書展」を開催している。150点にものぼる作品は、米国書道研究会会員に加え、産経国際書会で活躍する日本の書家からも出品された。書家で米国書道研究会会長、及び産経国際書会副会長でもある生田博子氏に、書道について、書の道についてインタビューした。
独りから始まる
基礎が大切です。基礎があってこそ、どのようにも書けます。栄養がないと元気になれないのと同じで、ヒョロヒョロしていたらダメですね。しっかり栄養を取って、しっかり勉強して、しっかり肥やしをあげて咲いた花はキレイです。けれど、栄養不良ではキレイな花は咲かないです。全てが勉強でしょう。
日本人が書いた書と中国人が書いた書とでは違います。日本語は線が少し優しいですね。字にはその人の人柄が表れます。弘法大師の書は優しくて、動きがあって、なんとなく日本人らしいです。弘法大師の書を見ると、すぐに分かります。いろいろ習い、最終的に自分の書を書いていかないとなりません。ここから、生田博子という字ができてくるわけです。名前を見なくても、これは生田の字だと分かります。そこからが難しいですね。「一体、私は何だろう」となります。
これまでお手本を見て習い、先生から習いましたが、今はもう誰も何も言ってくれません。これほど、緊張することはないですよ。観周先生がいれば、「ここが少し荒れているぞ」とか言ってくれたでしょうけれど、今は何も言ってくれないので、本当に崖っぷちに立っているような気がします。私、これで終わりなのかな、これ以上できないのかなって。けれど、歳をとると少し書けるような気もしてきます。
賞をいただいて、少しは上手になったのかもしれませんが、もう誰も頼れませんから、良くても悪くても自分の心の判断で出展する。独りにならないとできません。だから、今からは生田博子でなければいかんのです。
産経国際書会副会長というのはプレッシャーです。それに恥じないように手綱を緩められない、だんだんとキツくなっていく。自分で判断するしかないですからね。自分で見ないとならないから、自分が太らないとダメです。自分が太っていないと、見る目がなくなってくる。変なものでも平気で出展してしまうと困るでしょ。それが怖いので、展覧会には必ず見に行きます。そして、第三者の目で見て、自分で判断します。観周先生と国井誠海先生が亡くなって独りになって、これからが勝負です。
できるだけ良い物を見ようと思います。尊敬する人がいれば、その人の作品を見ます。感性が鈍ってくると、目も鈍ってきて、気持ちもダメになるでしょうから、これが一番怖いです。常に研ぎすまし、磨くしかないですね。
誰かが書かないといかん
「創立五十周年記念日米合同書展」の一部。(左から)渡部美恵子「宿」、伊藤欣石「壽雲」、渡邊麗「芸術とは人間の存在そのもの」、生田博子「移り住む 国の民とし老いたもう 君らが歌う さくらさくらと」(皇后陛下が日系引退者ホームご訪問の折に詠まれた御歌)、生田観周「白雲片々領上飛」、佐々木月花「吐雲」
この頃は、近代詩を書く人があまりいませんが、国井誠海先生の系統なので残したいと思っています。近代詩は長くて集中力も体力も必要ですから、なかなか、皆さんが書きません。けれど、誰かが書かないといかんと思っています。
体力が若い時とは違いますから、今は後のことを考えています。米国書道研究会の会員には実力をつけてもらいたいです。私のことをあまり頼ってもらいたくないです。一人で歩けるようになってもらいたい。今はできるだけ皆さんが自分でやるようにしむけています。
私についてきてくれる人がいるかしら、本気でやってくれる人がいるかしらと、少し不安にもなります。今の人たちは、私たちとは違って恵まれていて、してもしなくてもよい環境にいますから、情熱を持ってやってくれる人があれば万々歳ですね。
観周先生が亡くなった時、一面では放たれたものもありましたけれど、責任がまわってきたような気がしました。観周先生は亡くなる前に「僕がいなくなったら、好きなようにやりなさい。やってもいいし、やらなくてもいい。自由にしなさい」と言っていました。けれどリタイヤはできないのね。これは人間の欲かしら?
投げ出すのは無理でしょうね。言うほど楽じゃない。以前は、後についていて前に出されたら困りましたが…やはり、やれるだけやるでしょう。私は何かによって生かされているのでしょう。だから私はこれから皆さんにご恩をお返ししなくてはいけないと思います。
=Tomomi Kanemaru