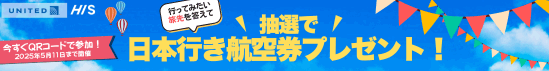「焼酎輸出促進協議会in LA」発足
2017-08-19
官民一体で焼酎ブーム作る
(左)アメリカにある日系の食品ディストリビューターが招待客に焼酎について説明した(右)焼酎を楽しむ招待客を一緒に乾杯する弥生焼酎醸造所の杜氏・川崎洋之さん(右から二人目)
アメリカで焼酎の普及と輸出を促進しようと、在ロサンゼルス日本国総領事館、日本貿易振興機構(以下、JETRO)ロサンゼルス事務所、日系食品商社、南加県人会関係者などの官民11組織から構成された「焼酎輸出促進協議会in LA」が、8月3日に発足され、第1回会合、セミナー、発足記念レセプションが開催された。
「焼酎輸出促進協議会 in LA」の第1回会合の様子=8月3日、ロサンゼルス市
日本政府はアメリカにおける輸出拡大戦略に「アルコール飲料」を重点品目に指定した。日本からのアメリカ向けアルコール輸出のうち、日本酒は2016年に約52億円を記録し、ウイスキーは近年の日本産ウイスキーブームもあり、2016年は2014年と比して4.5倍となる約28.7億円を記録するなど大幅な伸びを達成した。
一方、日本酒と同じ國酒でウイスキーと同じスピリッツ(蒸留酒)である焼酎は、2016年の対米輸出額が約3.5億円と日本酒の僅か7%弱と低水準に止まっている。しかし焼酎の日本国内消費量が日本酒の1.5倍強であること、アメリカではスピリッツがアルコール飲料市場を牽引していること、同スピリッツ市場で近年にメキシコ産テキーラが成功を収めていることなどを勘案すると、対米輸出について焼酎も今後は拡大余地が大きいとも考えられる。
このような状況を踏まえJETROロサンゼルス事務所では、今後の伸びしろが大きいとも言える焼酎にフォーカスした。焼酎の知名度向上や輸出に関わる課題抽出や問題解決への取組み、日本国内の蔵元の海外展開促進などに官民一体で取り組むため、「焼酎輸出促進協議会in LA」が発足された。
セミナーでは「海外進出成功のカギ〜米国を制する者が世界を制する〜」と題して、日本食文化振興協会理事長の雲田康夫氏が講師を務め、在米32年間で豆腐をアメリカに普及した経験を、焼酎のPRのため渡米した焼酎蔵元たちに語った。
会合では「焼酎輸出促進協議会in LA」の委員たちがアメリカの市場で焼酎を販売する上での課題について意見交換をした。
「ミレニアル世代」研究
アメリカではほとんどのアメリカ人がまだ焼酎の存在さえ知らず、在米邦人が焼酎の消費者だ。どのようにしてアメリカ人の焼酎の消費者を開拓するのか。
会合では、日系食品商社がB to Cのイベントの開催により力を入れる必要があるという意見が複数の協議会委員から出た。アメリカ人が焼酎を飲む機会を作り、焼酎好きの人々を増やせば焼酎の輸出拡大につながる。
現在、アメリカで消費を支えているのは1980年以降に生まれた30代後半までの「ミレニアル世代」。彼らの総人口はベビーブーマー世代より多い約9200万人でアメリカの全人口の3分の1を占めている。この世代は古いものにはこだわらず、新しいもの好きだが本物志向が強く、そのためには代価を支払うという。
焼酎の輸出拡大の鍵となる「ミレニアル世代」にどのように焼酎を紹介し消費を促すのか。
これまで商社も「ミレニアル世代」の購買活動などについて研究し戦略を練ってきたが個々では限界があるため、今後は「焼酎輸出促進協議会in LA」で一丸となり「ミレニアル世代」を研究し、焼酎の消費拡大を目指す必要がある。PRはSNSを積極的に使い、ブロガーなどが情報発信する。内容がおもしろければ短時間で大勢に広がるため安価で効率も良いという利点がある。
焼酎の教育
PRだけでは一過性のブームで終るため焼酎に関しての教育も重要な鍵となる。他州などではロサンゼルスと異なり日本食エキスパートが少ない。日本食がスーパーで販売されていても店員がお客の質問などに答えられず、販売が伸びないケースが多いという。
そこで焼酎を取り扱う食品商社の営業員を教育し、営業をする過程で接客店員にまで知識や焼酎の魅力を伝えられれば焼酎の知名度もアップされ販売促進につながる。
アメリカ人からよく聞かれる質問は「日本酒と焼酎の違いは何か」。
日本酒は醸造酒で米から作られ、焼酎は蒸留酒で原料が芋、麦、黒糖、そばなど53種類と豊富だ。「焼酎ほど元々の原料のうま味の出ている蒸留酒は世界にないですよ」と協議会委員が言うように、この点でウォッカ、ウイスキー、ブランデーなどの蒸留酒とも異なる。
焼酎蔵元の熱意と自信
アメリカで焼酎を普及するには、日本の焼酎蔵元の情熱も一つの鍵となる。最近アメリカでブームになったテキーラは海外に出荷されて150年だがこの10年ほどでやっと高級ブランドも作られるようになった。アメリカで焼酎を普及させるには2、3年のスパンではなく長期的な戦略が焼酎蔵元に求められる。継続は力なりだという。
日本の焼酎蔵元がアメリカに進出する際に不安になる一つに言葉の問題もあるだろう。しかしテキーラのイベントで見られるのは、英語が決して流暢ではないが懸命に話しているメーカーのブースには多くの人が集まるという。このような地道な活動が今日のテキーラブームを作った。
「焼酎のように1回しか蒸留をしないアルコールは世界でも稀です。たった1回の蒸留でしっかりした味を出せるのは素晴らしい。そこまでのクラフトマンシップを持っているのは日本人しかいないでしょう。焼酎蔵元にはもっと自信を持っていただきたい」と、アルコール専門の協議会委員は語った。
他の課題としては、焼酎が日本酒と異なり取扱にハードリカーライセンスが必要となる点だ。多くのレストランはアルコール度数24%以下を扱うソフトリカーライセンスしか持っていない。ハードリカーライセンスは取得が難しいので、制度改革などを日本政府がアメリカ政府に働きかけるのも必要だ。
今回、「焼酎輸出促進協議会in LA」が発足されたことで、今後は官民が協力して同じ目標に向って活動することができるようになった。アメリカで日本酒がブームになるまで40年間がかかったが、焼酎ブーム到来は早まる可能性がある。
◆会合の進行役を務めた西本敬一JETROロサンゼルス事務所所長
「日本でも議論はありましたが、現場感覚がある議論ができたのは初めてです。ロサンゼルスの地元の方々の見識が重要だと確信しました」
Discover SHOCHU!レセプション
8月3日、総領事公邸にて、ハリウッドの映画関係者、レストラン関係者、ブロガーなどが招待されて焼酎レセプションが開催された。焼酎は鹿児島県奄美や宮崎県の焼酎とアメリカで販売されている焼酎が振る舞われた。
宮崎と鹿児島から渡米した焼酎蔵元が自慢の焼酎を招待客にPR
=Tomomi Kanemaru