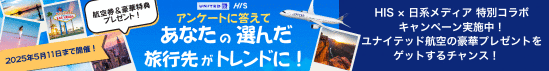日系社会のフロンティアを尋ねる vol.3 - ダグラス・アーバー 南加日米協会プレジデント
日系社会で活躍するリーダーと各界で活躍する日系リーダーを尋ねるシリーズ。第3回目は、南加日米協会(Japan America Society of Southern California、以下JAS)のプレジデント、ダグラス・アーバー氏にインタビューした。
ハリウッド生まれ。母方の祖先はメイフラワー号の直後にアメリカに移民。遠い親戚の祖先は太平洋へ陸路での探検をしたルイス・クラーク探検隊のメンバーだった。1989年には愛知県安城市で英語指導助手を務める。2002年にはJASプレジデントに就任。
日本訪問で人生変わる
―新年、明けましておめでとうございます。
(日本語で)明けましておめでとうございます。
―JASに関わって今年で23年目ですね。日本に興味をもったきっかけを聞かせください。
小学2年生のとき、日系アメリカ人の友人、ジョー・カワサキに出会いました。初めて日本文化に触れました。ジョーの母親は日本から来ていて父親は日系二世でした。ジョーの家に行くのはおもしろい体験でした。靴を脱いで家に入ったり、新しいことばかり。調味料も違うにおいがしたり、日本語が書かれているクラッカーがあったり。あとでせんべいだと知りましたが(笑)。日本に興味がありました。ジョーに感謝です。
17歳のとき、私は学生大使としてハンティントンビーチ市の姉妹都市の愛知県安城市に行きました。高校のときにペンフレンドが日本にいたので日本を訪問したいと思っていました。けれどその資金がありませんでした。ある日、母が新聞でハンティントンビーチ姉妹都市協会のことを見つけて、それで応募しました。
この旅が私の人生を変えました。アメリカに戻ってきて、それまで勉強していたスペイン語をやめて、新しい友人たちとコミュニケーションするため日本語を勉強し始めました。
大学に通いながら日本にサーフボードを輸出していました。そのとき安城市から中学校で英語を教えてほしいと頼まれたので、大学卒業後、安城市で英語の先生をしました。初めてスーツを買いました。それまでサーフィンをやっていて、いつもTシャツでしたから(笑)。スーツを着て小さすぎるスリッパを履いて学校で教えました。その時の体験は特別で宝物です。日本人を理解するよい機会となりました。
1991年、ハンティントンビーチに戻るとJASのことを知り、インターンを始めました。
―選択が他にもあった中で、なぜ日本なのですか。
初めて日本を訪問したことで私の人生は変りました。おもてなし、親切心、誠実な友好関係がなにより印象的でした。私は古い伝統を重んじるというより保守的です。もし友人になったら強い絆を大切にします。これは日本から継承したと言えます。日本人は中学を卒業して30年経っても友人関係があり、そこに首相になった生徒が来ても恩師は恩師で、恩師を「先生」と呼ぶでしょう。このような価値観が私にはとてもしっくりくるのです。
愛知県で英語を教えていた頃、私は自分自身を“一人の外交官”と意識して人々に会いました。日本人は私を通してアメリカがどういう国なのかを感じますから。アメリカに帰国したら、知り合いから「日本にはたくさんの“チャイナマン”がいるの?」と質問されました。これを聞いて固定観念を壊すためにアメリカですることがたくさんあると認識しました。当時、日本は経済大国になったけれど、アメリカ人が日本について知っているのは、ゲイシャガール、ソニーウォークマン、日本車。アメリカ人は日本人についてほとんど知りませんでした。だからJASの存在を知って、私にぴったりだと思いました。
苦しいときも支える
―JASについて教えてください。
 JASがメインオーガナイザーとなり他の団体と共に天皇・皇后陛下を招き晩餐会を開いた。右端はピート・ウィルソン カリフォルニア州知事=1994年、ウィリッシャーホテル(アーバー氏撮影)
JASがメインオーガナイザーとなり他の団体と共に天皇・皇后陛下を招き晩餐会を開いた。右端はピート・ウィルソン カリフォルニア州知事=1994年、ウィリッシャーホテル(アーバー氏撮影)メンバーの35%は日本人で残りはアメリカ人です。日本、日本人、 日本文化、日本食などに興味が ある人、日本に住んでいたことがある人です。また日系企業に勤務で上司との関係など理解を深めようとしている人。学生からシニアまでいます。JASはすでに日本と日本人に親近感を持っている“アメリカ人へのドア”と見られているようです。
―活動について教えてください。
日本が自然災害に見舞われるたびに、JASは日本の被災地の人々に救援物資や義援金を送り支援してきました。80年代の日米間の“貿易戦争”のときは日本人とアメリカ人が強いポジティブな関係を維持するよう支援しました。貿易戦争は政治的なことです。人と人とのつながりは全く変らないのです。
第二次大戦中、JASは活動を休止して、Japanese American Citizens Leagueに全ての資金を寄付しました。同時に日米に関する協会の全ての記録を保管したのです。敵国であった日本の資料を保管するなど、決して支持される行為ではありませんでしたが…。
戦後に迎えた本当の終戦
―印象に残っている活動は。
2004年に、日本海軍航空隊とアメリカ海軍航空隊の“最後の再会の集い”を開催しました。日本から元零戦パイロットたちが平和の願いと善意とともにアメリカを訪問しました。当初、さまざまな日系団体に参加を呼びかけましたが、最終的には日米協会が単独でこのイベントを行いました。
チノ・エアショーで、日本人の若者パイロットが当時の制服を着て、零戦に乗り込み、大空を飛びました。その時、日本人の元零戦パイロットたちの目からは涙がこぼれていました。一緒に渡米した夫人は零戦が空を飛ぶのを見て、あまりの美しさに感動して「あなたが零戦で飛んだことを話すたびに『うるさい』と60年以上も言い続けてごめんなさい」とご主人に謝ったそうです。
このとき、JASは日米の退役軍人が会う機会をいくつか設けました。私はいくつかのアメリカの退役軍人グループに出席を呼びかけました。1/3は「出席する」という返事でした。1/3は「たぶん」、のこりからは電話を切られてしまいました。けれど、最終日のランチに「たぶん」と返事した退役軍人たちも姿を現したのです。180cmもある70歳以上のアメリカ人の退役軍人が150cmの日本人の零戦パイロットをハグしたのです。二人とも泣いていました。そして「私にとっての戦争がやっと終わった」と言いました。精神的な武装が完全に解き放たれたのです。みなさん泣いていました。私も泣きました。東本願寺で、平和と慰霊の儀式も行いました。最高の経験の一つとなりました。2007年、再び、私はJASの会長と一緒に、日本へ彼らを訪ねました。けれど、もうほとんどの方が亡くなっていました。
—2014年の決意は。
 1994年の晩餐会で公式カメラマンを務めたアーバー氏は、「“人生で一度のチャンス”と思い情熱を持って撮影しました。一晩で36本のフィルムを使いました」と話した。公式写真にアーバー氏が撮影した写真が選ばれた
1994年の晩餐会で公式カメラマンを務めたアーバー氏は、「“人生で一度のチャンス”と思い情熱を持って撮影しました。一晩で36本のフィルムを使いました」と話した。公式写真にアーバー氏が撮影した写真が選ばれた昨年7月にはTOMODACHI―NAJAS福島学生文化交流プログラムを開き、児童擁護施設福島愛育園から8人の子供を招待しました。私が17歳で日本訪問をして人生が変わったように、彼らも人生が変わる体験をしました。同時にホストファミリーやボランティアにとっても人生が変わる体験でした。このようなボジティブな活動を今年も続けます。
2月13日は笹川平和財団からの助成金で「JAPAN in 2014 Symposium」を開催します。日本についてのエキスパートたちを招待し、今年の日本について予測します。藤崎前駐米日本大使とルース前駐日アメリカ大使のディスカッションもあります。また、国際交流基金日米センターからの多額のグラントで今年は新メンバーの入会を推進するキャンペーンをします。
=Tomomi Kanemaru
2014/01/11 掲載