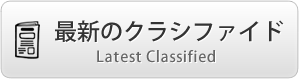苦楽歳時記
Vol.35 スイングしなければ意味がない
2013-05-28
今、書斎にペッパー・アダムスのバリトン・サックスが流れている。日ごろから物を書くときには、ジャズを流して執筆にいそしむ。眠りにつくときも、ドライブをするときも、そして食事をする折りにも、日がな一日ジャズを聴いている。
病院のICUにいた際も、ヘッドフォンをつけてジャズに酔いしれた。ジャズに看取られて逝くなら本望だと思った。
ジャズを聴いている最中に、よく詩が浮かんでくる。昨日と一昨日は、一行詩が淀み無く浮かんできた。「桃の実は木から病も気から」、「天国で安心して不安に過ごしたい」、「考えて考えあぐねて日が暮れた」、「星ひとつ遥かかなたに片恋のついおく」。
僕が一行詩を始めた弾みとなったのは、尾崎放哉の無季自由律の俳句を読んでからである。かれこれ、三十七年前にさかのぼる。かの有名な「咳をしても一人」、「いれものが無い両手で受ける」。僕はこれらの句に魅了されてしまったのだ。
放哉の句を初めて読んだ折りに、待てよ、と思った。無季自由律の句なのに、「咳」は冬の季語であるからだ。僕はしばし考えた。多分、放哉は「咳」を季語と意識して、作ったわけではなかろうと察した。
僕が俳句を作りだしたのは大学生の頃に、俳句同好会の朋友に誘われて、句会に主席したのが契機となる。時を経て、ひょんなことから、俳人の近松寿子さんと知り合いになれた。隔月に催される『連句の会』では、鮨屋の二階で酒を酌み交わしながら、鮨をつまんでは連句を巻いた。往時、僕と連衆が巻いた歌仙は、近松寿子著編『連句をさぐる』に掲載されている。
渡米後、俳句とは疎遠になっていたが、四年半前に悪疾に見舞われてから、再び俳句を作る誘因になった。「癌病みて神の計画に喝采」。これは病院のICUにいた折に作った俳句。
ジャズと詩と俳句はそぐわないというけれど、僕の感性にはスイングするのである。人生も文学も、スイングしなければ意味がない!
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。