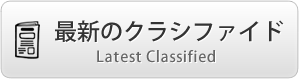苦楽歳時記
Vol 58 悲しみを友として
2013-08-16
今から九年ほど前の夜半、寝室のバスルームで咳き込んだ際に、傍らにいた三歳の娘が「咳をしても一人」と口走った。尾崎放哉の自由律の句である。
娘が最初に暗誦した俳句は「柿くへば鐘がなるなり法隆寺」(正岡子規)。遊び半分で始めたつもりだったが、三つ子の魂は水を吸い取るスポンジの勢いで、次から次へと俳句を吾がものにしていった。
「眞砂(まさご)なす数なき星の其(そ)の中に吾に向かひて光る星あり」。子規の短歌が思わず口からこぼれた。正岡子規の短い後半生は病との闘いであった。二十一歳のときに大喀血した子規は、血を吐いて死ぬ時鳥(ほととぎす)から、同じく「ほととぎす」と読む「子規」と号した。
三十一歳の頃から、三十四歳で不帰の客となるまでの約三年間、結核は脊髄(せきずい)を蝕み、激痛に号泣しながら塗炭の苦しみをなめた。
「病床六尺、これがわが世界である。しかもこの六尺の病床が余には広すぎるのである」連日、病床に呻吟しながら、新聞『日本』に連載した『病牀六尺』は、正しく子規の絶叫であった。
「病人は健康な者よりも自己の魂により切迫するものだ」。このようなことを述べたのは、フランスの作家プルーストだ。
一九八九年、四十五歳のときに、大野勝彦さん(詩画家)は農作機で両前腕を切断、失意のどん底で自己の魂に切迫し続けた。病や不慮の事故などで肉体が苦痛の極限に達すると、煩悶の果てに精神が解放されて浄められる。
やがて彼が表現する詩歌や絵画の数々は、人々の心に感動を与えて、生きていくことへの勇気と希望をもたらしてくれる。
スペインの女流詩人カストロは詩に書いている。 運命にもてあそばれ 賤しい芒(のぞき)のように/わたしは さびしく さまよった/けれど すべてをつれていた わたしは/悲しみを 友として つれていたから(長南 実訳)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。