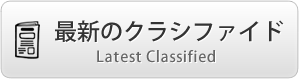1000字で文学名著
第8回 『ライ麦畑でつかまえて』 J・Dサリンジャー
2016-08-16
筆者の青春時代における愛読書のひとつに、J・Dサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』(原題:『The Catcher in the Rye』)がある。純真無垢なものへの強い要求と虚構に対する憎悪が、魅力的な風刺となって描かれていく青春小説である。
筆者は十六歳の主人公、ホールデン・コールフィールドへの風貌から思惑、挙措にいたるまで全ての描写が好きでたまらなかった。いや、その象徴とやらに惚れぬいていたかも知れない。
本作品を初めて読んだときの爽やかで、身も心も軽やかになった読後感は、今でも、筆者の記憶の小箱の中にとじ込められており、読み返してみる度に、ひとつひとつの活字が鮮明な色調をおびながら、悪戯っぽく筆者に迫ってくるのがわかるのである。
フォークナーは現代文学の最高傑作として、『ライ麦畑でつかまえて』を称揚しているが、他方では粗野な言葉をまき散らかす、不良少年の気まぐれ物語としてしか理解されず、この作品を学校図書の禁書目録に載せる学校や地方自治体が現れた。
ここで簡単なあらすじを記したい。
ホールデン・コールフィールドはクリスマス近くに、三度目の高校を除籍となる。自宅のあるニューヨークへ戻るも、「インチキで汚い世界」に絶望しながら、なお、「人恋しい」気持ちから他者との心のふれあいを求めて三日二晩をさまよう。
現代社会の虚偽、虚飾、無神経、弱肉強食、卑俗など、彼はいささかも受け入れることはできなかった。
放浪中、孤独のあまりに近づいてくる人々も、金だけが目当ての淫婦やポン引き、ことの本質が見抜けない女友達と教師。それでも修道女、子供、凍てつく池のアヒルなどの非力なものへの慈しみは忘れていない。
彼はしだいに人間不信に陥る。原因としての「言葉」の放棄である。幼い妹、フィービーの顔を思い出して、その想いだけにとどまる。
他にもこの小説と、ホールデン・コールフィールドの魅力を伝えなければならない。しかしながら、本稿は誘い水であるので読者の皆さんは、青春時代に戻ったつもりになって、『ライ麦畑でつかまえて』を存分に謳歌してほしい。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。