1000字で文学名著
第9回 『草枕』 夏目漱石
2016-09-20
今年は、夏目漱石没後百年、来年は生誕百五十年にあたる。
「草枕」の冒頭はあまりにも有名だ。
「山路(やまみち)を登りながら、こう考えた。
智(ち)に働けば角(かど)が立つ。情(じょう)に棹(さお)させば流される。意地を通(とお)せば窮屈(きゅくつ)だ。とかくに人の世は住みにくい。」(原文)
人の世はすみにくいとどうなるのか。
「住みにくさが高(こう)じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟(さと)った時、詩が生れて、画(え)が出来る。」(原文)
この小説は、熊本県玉名市小天温泉を舞台にして描かれた。「非人情」の世を描出している作品である。難しい文章があるので、読みにくいと言う人のために要約を記したい。
日露戦争のさなかに、三十歳の洋画家である主人公が、山中の温泉に投宿する。やがて宿屋の若女将、那美と親しくなる。主人公は、出戻りの那美は美人ながら、「なんだか物足りなさを感じた」。
ある日、主人公と那美は、満洲へ出征するいとこの久一を停車場で見送る際、続いて思いがけず、那美の元夫の「野武士」のような顔が現れた途端に、那美の顔に「憐憫」(れんびん)がただよい、横で見ていた主人公は那美の肩を叩き、小声で「それだ、それだ、これがでれば画(え)になりますよ」。
主人公の胸中に「画面」を成し遂げる。
「草枕」は物語のあらすじよりも、文章の随所に芸術論、文学論や人生論。さらには漱石自作の俳句や漢詩の方こそ、西洋にはまだない俳句的小説だ。漱石が胸を張ったこの作品の命がある。
この作品は、奥ぶかくて興味をそそる小説である。読めば読むほどに味わいを増す著書。一読を推奨する。
【備考】
『草枕』の意味(旅先で、草に仮に編んだ枕の意味。旅寝すること)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
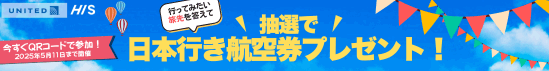
 文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。
文芸誌、新聞、同人雑誌などに、詩、エッセイ、文芸評論、書評を寄稿。末期癌、ストロークの後遺症で闘病生活。総合芸術誌『ARTISTIC』元編集長。








