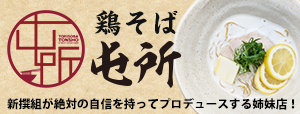編集部
パラリンピック正式競技・車いすテニス 20年の東京・28年のLAを目指す 日本・アメリカ・カナダの若い選手たち <7>
2018-01-28
国別対抗・国際親善試合「JTB 車いすテニス・グローバル・チャレンジ」(B Adapitve Foundation主催)に参加した日本、アメリカ、カナダの選手と関係者に、各国の車いすテニスの課題や抱負をインタビューした。毎日連載パート7。
坂口 剛さん
一般社団法人 日本車いすスポーツ協会 代表理事
車いすテニスクラブ「ウラテク」校長
ランチタイムに、カナダの車いすテニスチームの監督、スティーブ・マンリーさんが、いろいろの種類のピンバッチを日本チームの選手にプレゼント
―日本車いすスポーツ協会の今後の展開を聞かせてください。
坂口 障害がある子どもたちが一人で留学ができる仕組みができないかと動いています。
物事を、日本という小さい所ではなく、もっと大きな視野で見ることが必要になる状況が、障害のある子どもたちには増えてくると思います。
健常者だと学校単位の交換留学や個人での留学の機会がいくらでもあります。障害者でも大学生の年齢だと留学している人はいます。
しかし、中学生や高校生の障害者が、スポーツと勉強の両方を頑張りたいと言っても受け入れ先がありません。自分が心の底からやりたいと思っていることに対して、自分で道を作っていくチャンスがないんですよ。選択肢がないんです。
健常者の留学との差は、障害者の子どもには、受け入れ先となるホストファミリーがいないことです。
「障害のある子を受け入れられますか?」と尋ねられたら、内部障害のこともあるので、よほどの覚悟と知識がないと、リスクが高すぎて、ハードルが高いです。
けれど、今回のように、選手が親元を離れて海外のテニス大会に参加したように、本人が「大丈夫です、自分でやれます」と言ったならば、受け入れ側も、とりあえず1ヶ月だけで、1週間だけでもやってみようかとなるかもしれない。
そうなったら、可能性が広がります。そのチャンスをなんとか作りたいです。
(2018年1月30日付けにつづく)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 日刊サン編集部
日刊サン編集部