今月の庭仕事
Lesson 202
2018-01-10
新年あけましておめでとうございます。この言葉の持つ意味が最近ようやく分かってきた気がします。新年を迎えることができなかった人の想いを胸に秘めながら、今年も前に進んでいきましょう。
あなたの庭に思い出のプラントなどが植わっていませんか?子供や孫が生まれた時、どなたかが亡くなられた時、人生の節目に植えたプラントがあれば、庭を眺めた時の思いも違ってきます。記念に木を植えてみるのもいいでしょう。人間より長生きできるのは木だけです。
さて1月にしておかなければならないことについて書きますと、落葉果樹の剪定、春の病害の発生を未然に防ぐための休眠期病害虫駆除剤の散布、寒肥を与えることです。
剪定は実の生り具合を調節するためのものです。葉が落ちた後の枝を見ると、どこに実が生るかが、ある程度分かります。剪定の本に詳しく説明があるので本を参照しながら剪定してみましょう。木にも本能があるので、実があまりにも生りすぎると、木はすべて育成できないと判断して余分な実を落果させます。人がこの作業をすると摘果と呼ばれます。
春に効肥状態になるように有機肥料を寒肥として与えます。いつも書きますが、肥料はプラントが必要としている時に、ルーツゾーンにあげましょう。ここで言う肥料は、リン酸肥料が主で窒素は二の次となります。リン酸肥料としてはボーンミール、窒素肥料としてはチキン、ステアマニュア、ブラッドミールのような感じでいいでしょう。
「今年はやってみようか」と重い腰を上げてくれる人が出てくれば、書き手としてもしめたものです。一度やってみたら、やらないのとは大違いだと実感します。
ここからが効果があるか、ないかの分かれ目となる話をしましょう。
肥料を木の周りのバラまいて、“やったつもり”になっている人が多いかと思います。肥料は、春先まで根の周りに留まっていなければなりません。雨が降れば、肥料が土に浸み込む前に流されてしまいます。解決策は、簡単。穴を掘って埋めれば固定できます。肥料の使用量、穴の数、穴の深さなどは木の大きさによって変わります。
肥料が効いて多くの花が咲き、実が生り始め、緑の葉ができ光合成でエネルギーの生産ができるようになったと思ったら、葉が病気に侵されて実が害虫に食い荒らされることも起きます。剪定、薬剤散布、寒肥は“三位一体”だということ忘れないでください。バラも忘れずに!
■コラムニスト:南加庭園業連盟の新垣安徳さん。「今月の庭仕事」の18回目から、自分の経験を元にコラムを書いていて、失敗&成功例まで経験豊富!
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
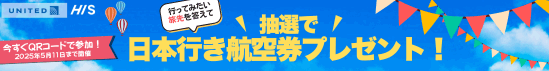
 SCGF: Southern California Gardeners' Federation
SCGF: Southern California Gardeners' Federation








