ピアノの道
vol.8 お休みの必要性
2019-04-17
“Music is not in the notes, but in the silence between (音楽は音符にではなく、音と音の間の静寂にある)。” 禅問答の様なこの名句は一般的にはモーツァルトが言ったとされていますが、ドビュッシーやマイルズ・デイヴィスなどにも非常に似た言葉があります。
色々な解釈が可能な味わい深い言葉です。日本の美学にある「間」の事を言っている感じもします。または「時間の芸術」である音楽は技術ではなく心にあるんだよ、と意欲的な若い音楽家志望者にくぎを刺している感じもします。でもこれ、脳神経科学でも説明が可能なんです。
交響曲を聴いている時、私たちの脳が一番活性化するのは、楽章と楽章の間なんだそうです。つまり、静寂ですね。更に(これはネズミの実験なのですが)毎日2時間無音の状態に置かれると、海馬と言う脳の中でも特に記憶を司る部分の細胞の活性化と新細胞の製造が見られるのです。情報のインプットと言うのは常にあります。インプットが無い時間にそれまでの情報の消化をするべく、脳が活性化するんだそうです。
ミスタッチをした時、反射的にすぐ弾きなおしたくなります。でもこれ、『練習』にはあまりなっていないんです。ミスをしたら、まず手を止めて何故間違えたのか、どうしたら同じ間違えを二度としなくなるのか考える時間を取ると、練習の効率がぐっと上がります。「音出し=練習」じゃないんですね。それから集中力を高めるために無駄なインプットを省くと言う意味で、音楽の演奏や鑑賞中に、目を閉じるのは効果があります。
一時期は朝から晩まで根性ものの漫画の勢いで血眼に練習していた私ですが、最近やっと余白の大切さが実感できるようになってきました。桜が一番美しいころに日本でのお仕事を頂き、私にとっては渡米30年後にして初めての日本の桜を、見て参りました。水路や公園・学校・路地...可能な場所に桜を植えつくす、日本人の桜を慈しむ心を愛しく思いました。写真でおすそ分けさせてください。
この記事の英訳はこちらでご覧ください
https://musicalmakiko.com/en/?p=983
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
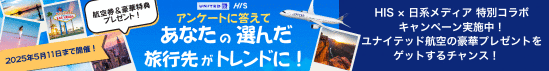
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








