ピアノの道
vol.23 ゆく年・くる年
2019-12-18
「All is well that ends well(終わりよければ全てよし)」はシェークスピアの戯曲の題名ですが、ことわざの様に通用しますよね。2019年のカウントダウンが近づく中、この言葉を考察してみましょう。
演奏の醍醐味の一つに、曲が終わった瞬間の会場の一体感があります。最後の音が消えいった後の余韻を会場全体で惜しむ静寂の数秒。逆に派手な曲の場合は、最後の和音が鳴り終わるのが待ちきれずに喝采と歓声が一斉に始まる時もあります。
でも、曲の中の細かい「終わり」は、私はずっと注意されっぱなしでした。「もっと『語尾』を大事に」「小節の最後の拍を微妙にはしょる癖を直せ」「Patience!」私の音楽人生の色々な恩師に、小節やフレーズやパッセージなどの終わりをよく注意されました。私はいつもせっかちに次ばかリを考えていたんです。最近ようやく一つ一つの細かい終わりをきちんと慈しんでから次に行くことを覚え始めた気がします。音は発音だけではなく余韻が消え入るところまでが大事なんだって。時と経験を積まなきゃ分からない事ってあるのだな、と思います。次を楽しみにする気持ちが減ったわけじゃない。でも過ぎ去るものに敬意と愛情と手間暇をかける楽しさが分かってきている。
「ピーク・エンドの法則」の心理学によれば、実際の経験が思い出に転換する時に大事なのは①感情の最高・最低時と②最後の2点になります。残念な事に生存本能が良い記憶より悪い記憶を優先させてしまうことが多いので、例えば奏者の場合、お客様には喜んでいただけても奏者本人は一瞬のミスタッチにくよくよしたりします。でも、これは「良い思い出に集中しよう」と心がけるだけでかなり改善できるそうです。最低時ではなく、最高時の事を常に思い出すようにするんです。
この文章をお読みくださっているあなたにとって2019年の最高時はどんな時でしたか?これからどうやって2019年を終えようとしていらっしゃるのでしょうか?2020年の何を楽しみにしていらっしゃいますか? 楽しいホリデーシーズンを!そして良いお年を。
この記事の英訳はこちらでお読みいただけます。
https://musicalmakiko.com/en/?p=1321
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
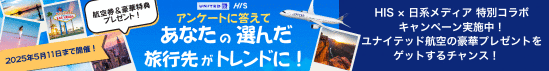
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








