What’s Up, 神主さん?
第3回 神道は宗教? (後編)
2019-12-27
神主兼映画ジャーナリストの、はせがわいずみです。10月から始まったこのコラムでは、日本の伝統文化や慣習、神話などをご紹介していきます。
前回、日本に帰省した時には神社に参拝してもロサンゼルスでは「宗教」になるから参拝しないという会話を紹介し、創始者も創始年も聖書・経典もない神道は宗教か?というお話をしました。今回はその後編です。
もうすぐお正月ですね。年末に大掃除をし、門松や注連縄(しめなわ)・注連飾(しめかざ)りを玄関に飾ります。元旦に初日の出を見に行く人もいます。なぜ大掃除をするのでしょう? なぜ門松や注連縄を飾り、初日の出を「ありがたい」と感じるのでしょう?
雨が降った後、太陽が照らすと植物がもの凄い勢いで成長します。植物には、米をはじめとする穀物、柿などの果物、栗などのナッツという万物の食べ物を実らせるものがあります。古来、日本人は、こうした「実り」「豊穣」は何かの力によって成ると考え、その力を「神様」と呼んで感謝し敬ってきました。太陽、雨、実りの恩恵は、人種、国家、宗教に関係なく、誰でもが与(あずか)ります。寒い日は太陽の暖かさに嬉しく思い、日々私たちのお腹を満たしてくれる自然の恵みに感謝する。宗教なら、それを信じる一定の人だけが恩恵に与ることになりますが、自然の恩恵は生きとし生けるものすべてに与えられています。神道はそうした自然に感謝する生き方なのです。
すべてのものに神が宿ると考えてきた日本人は、新年にも神様がいると考え、神様を「歳神様(としがみさま)」と呼び、幸福をもたらしてくれると考えました。歳神様をお迎えするのに、自宅やオフィス、店を掃除し、「清浄な場所」という印として、また、歳神様への目印として、注連縄や注連飾り、門松を設置するのです。門松は、歳神様の依(よ)り代(しろ)でもあると言われています。掃除には使わないものを排除することで、新たな年にやって来るものが収まる場所を作っておくという役割もあります。
さあ、ここまで読んだ方には、初日の出の質問の答えが大体分かったのではないでしょうか? 太陽がなければ私達は生きていけません。そんな太陽を日本人は「天照大神(あまてらすおおみかみ)」と名付け、感謝し、敬意を払ってきました。太陽に感謝する心は、神道という呼び名で私たちの中に伝統文化・慣習として脈々と受け継がれているのです。
2020年1月1日(水)に、リトル東京のオニズカ・ストリートに神社ブースを出します。ぜひ初詣にご参拝ください!
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
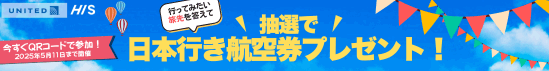
 世界で唯一の神主兼ハリウッドの映画ジャーナリスト。取材したセレブは、のべ1万人以上。実家は島根県にある出世稲荷神社。NHKなどのアナウンサーを経て渡米。スターのインタビューと写真を各国に配信する通信社を経営。WhatsUpHollywood.comの編集長や、島根県庁の古事記紹介サイトJapaneseMythology.jpの編集長を務める。神道コメンテーターとしてヒストリー・チャンネルに出演。アマゾン・プライムのドラマ『高い城の男』の神道コンサルタントを担当。島根県ふるさと親善大使「遣島使」。松江市観光大使。ロサンゼルス記者クラブ国際コラムニスト賞受賞。著書:ドラマ『24』の公式ガイド本『メイキング・オブ・24 -TWENTY FOUR-』(竹書房)。Instagram @IzumiHasegawa
世界で唯一の神主兼ハリウッドの映画ジャーナリスト。取材したセレブは、のべ1万人以上。実家は島根県にある出世稲荷神社。NHKなどのアナウンサーを経て渡米。スターのインタビューと写真を各国に配信する通信社を経営。WhatsUpHollywood.comの編集長や、島根県庁の古事記紹介サイトJapaneseMythology.jpの編集長を務める。神道コメンテーターとしてヒストリー・チャンネルに出演。アマゾン・プライムのドラマ『高い城の男』の神道コンサルタントを担当。島根県ふるさと親善大使「遣島使」。松江市観光大使。ロサンゼルス記者クラブ国際コラムニスト賞受賞。著書:ドラマ『24』の公式ガイド本『メイキング・オブ・24 -TWENTY FOUR-』(竹書房)。Instagram @IzumiHasegawa








