ピアノの道
vol.38 歴史と文化:広島原爆記念日にちなんで
2020-08-05
“History is written by the victors(歴史は勝者によって書かれる)”という言葉を思い出しました。最近、BLM(ブラックライブズマター)運動に関して友達と会話をしていた際です。「歴史というのは物語。単純さが必要。全ての視点を取り入れることは不可能。The Voiceless(声なき人々)が出てくるのは仕方ない」と言われ、その歴史の欠陥を補うのが文化では無いか、と反論したのです。文化や芸術や創造性の社会的役割というのは、その声なき人々にも声を与えることではないか、とその時思ったのです。
「75年は草木も生えぬ」と言われた広島の原爆投下から今日でその75年が経ちました。「はだしのゲン」の漫画や映画。「怒り地蔵」は国語の教科書に載っていました。私たちの世代の反戦教育は戦争の残酷さを、子供の視点から描いたものが多かったと、振り返って思います。作者は当時の子供や一般市民...いわゆる「声なき人々」です。
終戦後、原爆の人害の報道に制限がかかっていたことを、私は最近知りました。爆発の破壊力を示す建物の写真などは良いのですが、広島市民の被害を写真や報道で出版する事は困難だったようです。ジョン・ハーシーが6人の広島市民の原爆後の物語を特集した「ヒロシマ」は、タイムズマガジン社が検閲を恐れ、6回シリーズの企画を急遽一挙に出版したそうです。「はだしのゲン」もジョン・ハーシーの「ヒロシマ」も、歴史を簡潔化しようとする動きに、文化の力で抗ったのだなあ、と思います。そう言えばベートーヴェンの時代のウィーンも出版物の検閲が厳しかったようです。この時代に器楽曲が著しく発展した背景には、言葉の無い器楽曲は検閲の対象外だったこともある、というのも最近知った事実です。「The pen is mightier than the sword (ペンは剣よりも強し)」ですね。
体制の検閲が入ろうが入るまいが、私たちの脳は世界をできるだけ簡略化する事で理解したつもりになって安心しようとする傾向があります。でもその時に、私たちの感情の揺れ動きや現実の複雑さやニュアンスを感覚的に捉えるのが、美術や文化なのではないでしょうか?私は音楽は人間性の底力だ、と信じています。
この記事の英訳はこちらでお読みいただけます。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
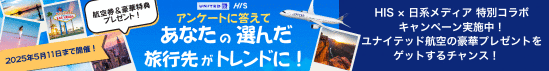
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








