ピアノの道
vol.69 感情ごっこ
2021-11-19
夏以降、演奏旅行が増えてきます。今朝の飛行機は早朝6時出発。ああ、それなのに目が覚めたらすでに4時半!済ませたと思った荷造りが全然出来ていない!そしてスーツケースが全て貯蔵食糧でパンパン!! 冷や汗をかきながら(…でも飛行機が遅れるかもしれない!)と何とか荷造りをしようとあがいていたら4時の目覚ましが鳴り、(ああ...良かった!夢だった!!)…心底ほっとしました。
聞きかじったところによると、夢というのは感情のバランスをとり、色々な可能性に対して心の準備をする役目があるそうです。音楽も同じではないでしょうか。
「なぜ人は悲しい音楽を聴きたがるの?」当時10歳だった生徒にされた質問をその後何年もずっと考えています。そもそも、感情的な音楽はなぜあるのでしょうか?一体感や癒し効果の為だけだったら、体の動きを統一する行進曲や舞踏曲、そして優しい子守歌の様な音楽だけで良いような気がします。でも激しい感情を訴える、魂の叫びの様な音楽というのはいつの世にもジャンルを問わずありますよね
一つには表現者(作曲家や奏者)の「言わずにはおられない」「分かってもらいたい」「分かち合いたい」という創作意欲があると思います。でもそれを受理したいと思う聴き手、その音楽を伝承したいと思う世代を超えたモチベーションはどこから来るのでしょうか?。
優れた表現者は、万人共通・古来永劫の感情の代弁者です。(ああ、この人も同じ痛みを体験したのだ)と思う事で救われる—それが癒しになるのだと思います。そしてまだそういう痛みを知らない人は、そういう感情を理解し甘受する練習を音楽体験を通じてする―そういう仕組みになっているのだと思います。これは悲しみや痛みだけではありません。怒りや、歓喜、恋愛感情、喪失感…そういう避けては通れない人生の様々な味を、音楽という感情のごっこ遊びを通じて、我々は練習するのだと思います
ちなみに6時発の飛行機にはちゃんと間に合いました!今その飛行機の中で書いています。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
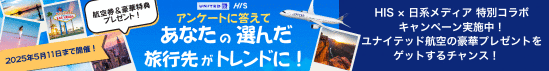
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








