ピアノの道
vol.71 聴き手の中にある音楽
2021-12-17
皆さんは虫の音を音楽だと思いますか?コオロギ、蝉しぐれは良いとして、蝿のぶんぶんは?夏の夜の枕元の蚊は?
1970年代に角田忠信博士が日本語を母国語とする人は虫の音を言語を処理する脳の部位で、日本語以外を母国語とする人はノイズとして処理しているという見解を発表しました。この主張は科学界ではその研究方法に技術的な批判が出ましたが、現在では息子さんがより発達された手段と医療機器で同様の見解から研究を引き継いでいます。
この主張の科学的根拠はともかく、日本文化の方が欧米に比べて微妙な音環境を愛でるというのは本当だと思われませんか?例えば茶道では、お湯の沸く音、お湯を注ぐ音、お茶を点てる音の全てがおもてなしと考えられているそうですね。
西洋人にも虫の音を音楽とか言語として愛でることは可能なんでしょうか? …可能なんです!カナダはブリティッシュ・コロンビアで1960年代に発祥したサウンドスケープは、音を通じて人間と環境の関係性を探ろうという試みです。彼らが掘り起こした自然界の音響は人間が自然界に負わせている痛手と損失を明らかにしています。そう言えば環境保護運動の火付け役、レーチェル・カーソンの1962年の名著は、農薬の副作用で鳥が大量死している現実を『沈黙の春』というタイトルに込めています。
耳を傾けることは世界と繋がり、周りを慈しむ行為です。イヤフォンやヘッドフォンを外し、スマホから顔を上げて、聴いてみて下さい。雨脚、風、木の幹のたわむ音を愛でてみて下さい。蝿や蚊でさえも居なくなったら寂しいとは思いませんか?
この記事の英訳はこちらでお読みいただけます。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
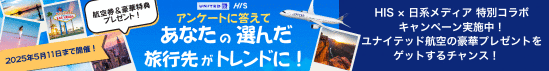
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








