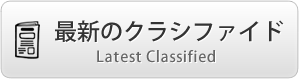受喜与幸 ~受ける喜び、与える幸せ~
vol.21 何も与えられなければ、ただそこにいればいい2
2022-03-18
ひざを擦りむいてお母さんに慰めてもらった子どもは、心の痛みとともに、体の痛みも実際に癒(いや)されていくのを感じるでしょう。それと同じことが医師と患者さんのあいだにも起こるはずです。
ただし、そのためには医師が単に医師で「ある」だけではダメで、医師に患者さんと「共にある」心がなくてはなりません。
患者さんと共にある……「言うはやすく、行うは難し」の典型ともいえますが、私自身、そのために心がけていることはあります。
たとえば、がんなどの重病の告知の問題。告知はがん医にとって実にむずかしく、また怖い問題でもあります。最近では、世間話でもするような調子で「あなたはステージ2の肺がんです」などとストレートに告げる医師が増えてきました。なかには、その場であっさり余命まで明かしてしまう若い医師もいます。
がんの告知は患者さんにとって、ときに死刑宣告にも等しいものです。その患者さんの心をまったくおもんぱかることなく、デリカシーも思いやりもなしに、平然と告げるのではやはり「共にある」行為とはいいがたいものです。
私は同じ医学的な事実であっても、できるだけソフトに、また直接的になりすぎないよう婉曲(えんきょく)に伝える努力をします。過大な期待を患者さんに抱かせない範囲で、先に希望をもってもらえるよう治療の可能性を強く伝えるのです。
「これだけの治る可能性があることは医師の私にとっても励みになります」
という言い方をすることもあります。ただ、その可能性がほとんどない場合にはどうするか。
これは永遠の課題です。患者さんができるだけ安心と希望の側を向いて話を聞けるよう心がけるのはもちろんですが、だからといって、いつわりの希望を抱かせることは死刑宣告よりもむごい場合があるからです。
現実には、いまのところこの病気が完治する技術はないが、いっしょに対応していくことはできます。そのプロセスで新しい治療法が生まれてこないともかぎりません。苦しい闘いになると思いますが、その苦しみをいっしょに受け止め、乗り越えていけるよう、こちらも力を尽くします。こうしてほしいというリクエストがあったらいつでもおっしゃってください……そんなふうに伝えるようにしています。
しかし、こうした究極のケースでは言葉やコミュニケーション上の技術はあまり有効な手段とはなりえません。
技術より大事なのは心で、医師が患者さんと共にあること、つまり身体的な治療者であると同時に精神的な同伴者でもあること。その思いをいかに相手に真摯(しんし)に伝えられるかが、医師にとってとても肝要になってくるのです。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 新原 豊(にいはら・ゆたか)
新原 豊(にいはら・ゆたか)