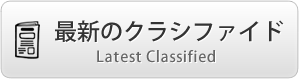受喜与幸 ~受ける喜び、与える幸せ~
vol.23 希望が限られた命の時間を深くする2
2022-04-01
三〇歳になるかならないかのころ、私はひとりの二〇代の女性の患者さんを担当しました。彼女の病気は乳がん、まだ初期の段階でした。
「これだったら十分治せますよ」
そう言って、私は患部の切除と抗がん剤を使った治療法をすすめました。一九八〇年代のことで、当時、乳がんの手術は温存技術が未発達で、切除しか選択肢がないのが実情だったのです。しかし、
「それは嫌です。絶対に困ります」
彼女は乳房の切除を拒否しました。妙齢の女性が片方とはいえ乳房を失う、その苦悩は十分すぎるほど推察できるつもりです。しかし、それに固執すれば、生命に危機が生じます。抗がん剤だけでは治らないがんであるのはあきらかだからです。
私は何度か説得を試みました。けれども、彼女はそのつど、「それだけはしたくない」と断固として乳房の切除を拒みました。
「そのままでは命にかかわりますよ」
「この胸が切られてしまうんだったら、生きていても意味がありません」
だから、死んでもいいから手術はしないというのです。若い私はそれ以上、説得する言葉を失って、彼女の意志にしたがいました。
抗がん剤の投与を続けることでいったん腫瘍(しゅよう)は小さくなりましたが、最初の見立てどおり、やはり完治することはなく、やがて肺に水がたまっているのが見つかりました。がんが肺へ転移したのです。
それから約一年後、彼女は永眠しました。末期のころは、私の顔を見るたびに「先生、ありがとう」と感謝の言葉を口にされていました。
彼女の死は私の胸中にさまざまな思いを残しました。喪失感と無力感。「本当にこれしか方法はなかったのか」という疑問、「なぜ説得できなかったのか」という後悔。
いちばん大きかったのは、「彼女の命にとってもっとも大切なことを彼女自身に気づかせてやることができなかった」―その無念の気持ちでした。
たしかに自分は「患部の切除はしたくない」という彼女の要求を受け入れた。そのかぎりでは、患者さんの意思を尊重した〝いい医者〟であるかもしれない。しかし、それは同時に彼女の生命にとっては最悪に近い選択であった。
だから、自分が真にすべきことは、彼女の要求にそのまましたがうことでも、自分の判断を一方的に押しつけることでもなく、彼女自身に「たとえ胸を失っても生きたい」と思ってもらうことであった。
乳房を失う喪失感を上回る、生きる希望と喜びの可能性を彼女に示すことで、その気持ちを「もっと生きよう」という方向へ向けることであった。それができなかった点で自分の治療は失敗だった……私にはそんなふうに思えました。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 新原 豊(にいはら・ゆたか)
新原 豊(にいはら・ゆたか)