ピアノの道
vol.78 記憶と記録
2022-04-01
皆さんはいくつの電話番号を空で言えますか?
文明史は記憶と記録の反比例の歴史です。私がそれに気づいたのは、博士論文で暗譜の歴史についてのリサーチを通じてでした。記録法が確立すればするほど、私たちは自分たちの記憶をないがしろにしているのではないでしょうか?外部の記録に過去を託すということは、すなわち自分の体験や感覚よりも数値化や暗号化できる『事実』を重要視する、ということではないでしょうか?
中世ヨーロッパの識字率は平均20%以下。日本ではそもそも文字の普及が6世紀まで始まっていません。物語や歌にして語り継がれていた人類の歴史や個人の過去が、人に頼らない記録として残せるようになったのは、情報技術の発明・発展とその一般化があったからです。例えば思考や音楽を、文字や音譜といった暗号にして記録する方法。解読を可能にする教育の一般化。その情報と記録を大量生産する印刷技術。今では我々はIT(インフォメーション・テクノロジー)無しでは生活できません。GPS無しで訪ねられるお店は何軒ありますか?
記憶にはいつも連想があります。私は子供時代のピアノの先生の電話番号を今だに覚えていますが、先生の歌うような裏声の「マキちゃん」や、寒い日のレッスンの前に淹れて下さった中国茶の湯気や香りを今でもありありと思い出します。でもスマホに見つける友人の電話番号には連想が少ないし、そもそも連想に想いを馳せる間もなく、テキストなど次の作業に入ってしまっています。記録法への依存は、我々の人間性や社会性を損ねていませんか?
生産性が最優先事項の現世で、多大な時間を暗譜に費やすピアニストというのは時代錯誤なのかもしれません。でも私はこういう時代だからこそ、暗譜という演奏様式やピアニスト人生に意義を見出したりもするのです。
この記事の英訳はこちらでお読み頂けます。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
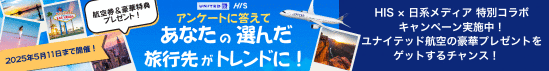
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








