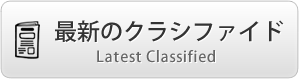受喜与幸 ~受ける喜び、与える幸せ~
vol.39 痛苦は尊大さをいましめる薬1
2022-07-22
病気をマイナスとしかとらえない人たちが多いのは事実です。
たとえば、自分の病気はもう治らないと悟った瞬間から、生きていたくない、治療なんか不要だと投げやりになって、必要な薬さえ「ムダだから飲まない」と拒否する。こうした患者さんはめずらしくありません。
気持ちはよくわかります。しかし、こういう人はいさぎよく病気を受け入れているように見えて、実のところ病気にあっさりと白旗を掲げているのです。生きる力をみずから放棄している。いわば体が死ぬまえに心が死んでいるのです。
実は、医者がいちばん困惑するのはこういうタイプです。生きよう、生きたいという気持ちが希薄なことが、もっとも病気の治療を妨げるからです。
そうかと思うと、健康を失った状態にひたすら不満を抱き、周囲に怒りをぶちまける人もいます。かつて私が担当した患者さんに、病気になるまえは社会的な地位も高く、権力もあって、自分の思うように振る舞ってきた人がいました。
こういう人はまず、自分が病気であることをなかなか認めようとしません。病気が意のままにならない存在だからです。わがまま勝手に生きてきたので、自分の思うとおりにならない病気というものが受け入れられない、またゆるせないのです。
そこで病気を自分でコントロールしようとする。「この痛みを何とかしろ」「もっと効く薬を使え」「もっといい治療法はないのか」―そんなふうに医者や家族に要求ばかりを突きつけ、不満を募らせていきます。
しかし、たいていの場合、そのコントロールはうまくいきません。そして、それを悟ったとき、はじめてのように底なしの恐怖にとらわれるのです。
自分の病気は治らない、死は避けられない。その事実を知ったとき、その患者さんは子どもみたいに手足をジタバタさせて、まるで命そのものにしがみつくように、「生かしてくれ、死なせないでくれ」と泣き叫びました。私や家族がなだめたり、慰めたりしてもいっさい聞く耳をもてないようでした。
きわめて残念なことに、こういう人の死もけっして安らかなものとはいえません。苦から逃れようとするばかりで、それと向き合う強さを十分にもつことができなかったからです。もっといえば、生に執着するばかりで死に目を向けてこなかったからだと思います。
こういう例を見ていると、病気に限らず、生きているあいだにわれわれが経験するさまざまな痛みや苦しみというのは、人間の尊大さ、傲慢(ごうまん)さをいましめるために人間に備えられたセンサーであるようにも思えてきます。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。

 新原 豊(にいはら・ゆたか)
新原 豊(にいはら・ゆたか)