ピアノの道
vol.97 天気で変わる音
2023-01-20
年末年始に続いた土砂降も晴れ、今はケロリと青空が広がっています。
空気中に水分が多いと、音波が共鳴させる対象が多くなって音は拡散し、くぐもったように聞こえます。その上、音波の細かい高音と音波の大きい低音では空気中の水分の影響が違うため、音域のバランスも変わるんです。更に、楽器自体が空気中の水分を吸います。特にピアノの場合、木やフェルトが水を含んで膨張し、ひどい時には摩擦で動きが鈍ってしまったりします。逆に空気が乾いた快晴の日は、音がスパーンと鳴り響きます。鍵盤も軽くなるんです。
どちらが良いとか悪いとかではなく、そういう事実を踏まえてじゃあどう奏でるか、という事です。与えられた状況の中でのベストを発揮する為には、まず状況を正しく見極めそれに臨機応変に対応する裁量と柔軟性が必要になります。
生演奏の醍醐味は、その日その時その会合の為の、金輪際再現不可な音楽を味わえることではないでしょうか。同じ会場で同じピアノで同じ曲を弾いたとしても、土曜日と日曜日では演奏が変わります。湿度だけでなく、例えば寒い日にお客さんが厚着をしてご来場されると、音波を吸う材質が増え音はこもります。更に、それぞれに個性がある一人一人が集まった群衆には、いつも違った性格があります。そういう聴衆から放たれる気という物は、奏者と演奏を大きな影響を与えます。お辞儀から頭を上げた際に見えるお客さまの表情。拍手のタイミングや調子。演奏中に聞こえて来る客席からのため息や、感じられる空気の緊張感。私が「演奏会は奏者と聴衆が一体となって創り上げる共同作品です」と壇上から訴えかけるのはその為です。
テレビやラジオやネットや録音は、受け取り手がどう反応しようが無関係です。それより生演奏の方が面白い…そう思う私は少数派でしょうか?
この記事の英訳はこちらでお読み頂けます。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
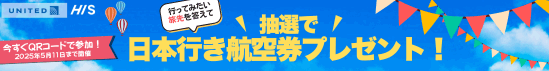
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








