マイ・ワード・マイ・ヴォイス
vol.46 亀裂(2)
2024-04-05
昔は良くて今はだらしなくなった、という言説を多くの人が安易に受け入れてしまうのは何故でしょうか。過去はノスタルジーというフィルターを通して思い出すことが多いから、現在と同じように様々な問題があったとしても全て削ぎ落とされ、美化されてしまうことがあります。バス停で私の後ろにいた男性もそういう意味で言ったのかもしれません。
だとすれば、ノスタルジーによる過去の美化は何が問題なのか。政局や経済状況、文化事象、コミュニティの在り方、時代精神、社会的マナーなど、全てをまとめて昔は「良い」、現在は「だらしない」と単純化することです。しかも、いつを「過去」とするのか、「良い」とはどういう意味なのか、本来であれば時代を区切り、具体的な分野の具体的な例を挙げて指摘する必要があるでしょう。そうした手続きを全て無視して語るなら、それはもはや時代に対する見解ではなく、個人的な意見ですらなく、その人の気持ちの吐露、もしくはファンタジーの表明に過ぎません。
そう、問題はこのファンタジーにあります。語るべき具体的な時代と視点が変われば様々な判断や見解が存在するはずなのに、「良い」か「だらしない」かに集約してしまうイメージ。世界はそうなっているというイメージ。そこには、細部を全て無視して「結局はこうなんだ」とまとめようとする強い意志が働いているように見えます。この意思のもとにあるのは何か?私たちは「結局、世界はこうなっている」という絶対の真理にいつか辿り着ける、という世界観ではないでしょうか。
多くの読者の皆さんが共有するであろうこの世界観を、リチャード・ローティは大胆に否定しました。哲学者たちはこれまで「絶対的な真理」に辿り着けるという希望のもと、様々な言説を展開してきた。理性を駆使して探求を続ければ、「真理」が明らかになる、と。彼らをそう信じさせたのは、人間の心が自然を正確に写す鏡のようなものであると考えてきたからだ、とローティは指摘します。そんな鏡は存在しないし、哲学はその鏡に写る「世界の正確な姿」をもとに私たちの知識を基礎づけする、つまり正しいと保証するためのものではない、と彼は言います。(続く)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
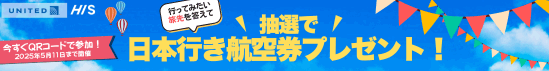
 哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。
哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。








