ピアノの道
vol.1313 蝶の声
2024-06-14
「私の蝶々!ピッタリな名前だ、繊細な蝶々…」
「お国では蝶を針に刺し自由を奪うと聞きました。」
絶大な人気を誇るプッチーニのオペラ『蝶々夫人』(1904)は15歳の没落藩士令嬢がアメリカ海軍士官の子を身籠り、約束を信じて帰りを待ちわび、裏切られて自害する悲劇です。人気の背景には、船乗り・進駐軍・植民地支配者と現地妻の不平等な悲恋の普遍性もあるのでしょう。更に『西洋=男』対『東洋=女』の構図が20世紀初頭の西洋優勢主義・植民地主義の欧米で流行したという歴史的背景も否めません。
アメリカで音楽の道を切り開こうと孤立奮闘していた私の立場も蝶々さんに似て弱いものでした。まだ駆け出しの私を蝶々夫人に連れ出したセクハラ興行師の前で、公演中怒りの嗚咽デモをしたことがあります。日本を矮小化するステレオタイプのオンパレードに悔し涙が止まらず、(理不尽全てに対する無言の抗議だ!)と泣きながら痛快に感じました。(もう二度と見ない)と思っていた蝶々夫人。でも今週末リトル東京のアラタニ劇場で千秋楽を迎えた「蝶々夫人」には足を運びました。
このプロダクションでは演出・衣装なども日本人の役も日本人や日系人が担当しているだけではなく、元々イタリア語の歌詞が日本語と英語の訳で歌われます。日本語訳を担当し指揮者も務めた磯村英木氏は「西洋の視点から書かれた台本に日本の真髄を求めるのは無理だが、日本人・日系人のキャストが台本へ視点を逆転させ協議を重ねたこの日英二か国語の解釈で登場人物に対する新しい共感が生まれれば本望」と綴っています。
舞台芸術の古典に於ける文化盗用(Cultural Appropriation)の問題と向き合う姿勢に賛同します。バレーのフィル・チャンは「Final Bow to Yellowface」というNPOを創立し、くるみ割り人形の「中国の踊り」などの見直しを要求する署名運動をしています。彼がボストンリリックオペラと手掛けた蝶々夫人の演出では蝶々夫人は1940年代のサンフランシスコの歌手なんです!
この記事の英訳はこちらでご覧いただけます。
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
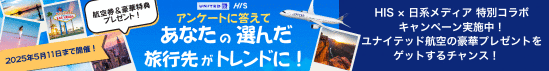
 日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。
日本生まれ。香港育ち。ピアノで遊び始めたのは2歳半。日本語と広東語と英語のちゃんぽんでしゃべり始めた娘を「音楽は世界の共通語」と母が励まし、3歳でレッスン開始。13歳で渡米しジュリアード音楽院プレカレッジに入学。18歳で国際的な演奏活動を展開。世界の架け橋としての音楽人生が目標。2017年以降米日財団のリーダーシッププログラムのフェロー。脳神経科学者との共同研究で音楽の治癒効果をデータ化。音楽による気候運動を提唱。Stanford大学の国際・異文化教育(SPICE)講師。








