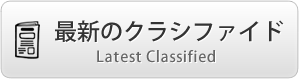マイ・ワード・マイ・ヴォイス
vol.53 演じる(2)
2024-11-01
高峰秀子が自らの演技の特徴を説明した「素人の自然さにパン粉をつけてフライにしたり、塩や砂糖や唐がらしをきかせたりして『見せもの』に仕立てた『真実』に近い嘘」という言葉は非常に示唆に富んでいます。彼女は自然な表情や動きを心掛けましたが、ただ自然なだけでは映画になりません。例えば彼女は『カルメン故郷に帰る』で主人公の能天気なストリッパー役を演じましたが、実際に東京で人気ストリッパーになった後、生まれ故郷に戻って地元の村人たちの前でストリップショーをする女性をカメラの前で筋書き通りに行動させたところで、映画は成立しないでしょう。「パン粉をつけてフライに」し、「塩や砂糖や唐がらしをきかせ」る、つまり味付けをすることで初めて映画となります。「自然さ」だけを追求するのではなく「見せもの」にもする。それでいて、単なる嘘にせず「真実に近い嘘」に仕立てる。この絶妙なバランスを保ったパフォーマンスを磨き続けたのが大女優・高峰秀子でした。
見せものとしての味付けの部分、つまり(もちろん映画なので)嘘ではありつつも、真実が宿る演技をする。観客である私たちはその嘘の中にある真実に心を動かされるのでしょう。では、演技の中にある真実とは何でしょうか?やはり『わたしの渡世日記』には次のようなエピソードも書かれています。生前から深い親交のあった谷崎潤一郎の告別式に参列した際、彼女は様々な思いがあふれ、谷崎の遺骨に向かって喋りかけてしまった。後日、その様子を見ていた大学の教授が「青山斎場で見た高峰秀子の泣き顔は、映画で見る彼女の泣き顔と全く同じであった。女優というものはあのような時でさえ演技をするものなのか」と書いた新聞の記事を読んで憤慨し、失望した。そして「私の真実の顔は、演技でも真実でも一つしかなかったのだ」と理解し、さらには「真実とウソ泣きの違いは実に紙一重であり、時と場合によっては、それはひとつにミックスされて、新しい真実となる。それが映画演技ではないか?と私は思った」と結論しています。「自然さ」と「味付け」、「真実」と「嘘」が融合した「新しい真実」こそが演技によって表現できる真実なのです。(続く)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
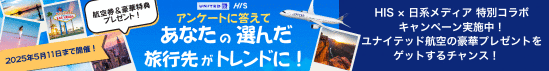
 哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。
哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。