マイ・ワード・マイ・ヴォイス
vol.54. 演じる(3)
2024-11-29
見る者の心を捉えて離さない高峰秀子の演技には、真実とウソが融合した「新しい真実」が宿っていました。ありのままの姿でも偽りの姿でもない、真実でもウソでもない、別の種類の真実。
映画『ドライブ・マイ・カー』でアカデミー国際長編映画賞を受賞した濱口竜介監督は著書『カメラの前で演じること』の中でこの真実に通じる映画の演出術を論じています。彼は演者に台本を読ませるとき「イタリア式本読み」という手法を使い、セリフに感情を一切込めずに読み上げさせ、それを何度も繰り返します。セリフの意味を考えてから演技プランを立てることはさせずに、言葉をそのまま音のつながりとして演者の体に覚えさせます。例えばタイピングをマスターした人が文章をタイプする時、言葉を意識して「まずは右手の中指でKを打って、それから左手の小指でAを打って『か』にして」という手順は踏みません。手自体がタイピングを覚えているかのように、頭に浮かぶ言葉がそのままキーを打つ動きに変換されます。同様に、感情表現を除いたセリフを何度も読み上げることで演者の身体自体にセリフが刷り込まれ、身体はセリフと一体化します。演者の声は厚みを帯び、身体はセリフを体現した物体となります。彼はこれを、演者がセリフのテキストを「はらわたに落とした」状態、「演者は演者のまま、テキストでもある」状態と呼び、その身体を獲得した演者を「テキスト的人間」と呼びます。タイピングをマスターした両手が文字を打つ動きを習得し、「か」と意識するだけで自然に右手の中指と左手の小指が動く準備ができているように。そしてカメラが回りだす。演者はお互いに「はらわたで反応し合」い、演者個人の声でもない、台本に書かれたウソの言葉の声でもない、第三の声が現れます。
高峰秀子はセリフを「はらわた」に落とし、自らを「テキスト的人間」に変容することができていたのではないでしょうか。だからこそ、友人の告別式で目撃された彼女の泣く姿と、スクリーンに映る彼女の泣く姿に違いを見出すことができなかった。どちらも彼女の身体が「自然に」動き出したからです。ここから、「演じる」ことの新たな意味が見えてきます。(続く)
※コラムの内容はコラムニストの個人の意見・主張です。
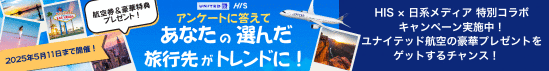
 哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。
哲学者。早稲田大学卒業後、サラリーマン生活を経て渡米。ニュースクール(The New School for Social Research)にて哲学博士号を取得した後、ニューヨーク市立大学(CUNY)をはじめ、ニューヨーク州・ニュージャージー州の複数の大学で哲学科非常勤講師を兼任。専門はアメリカンプラグマティズム、ジョン・デューイの哲学。現在は東京にて論文執筆、ウェブ連載、翻訳に従事。ウェブでは広く文化事象について分析を展開。








